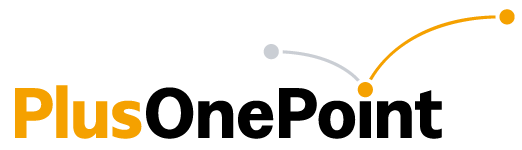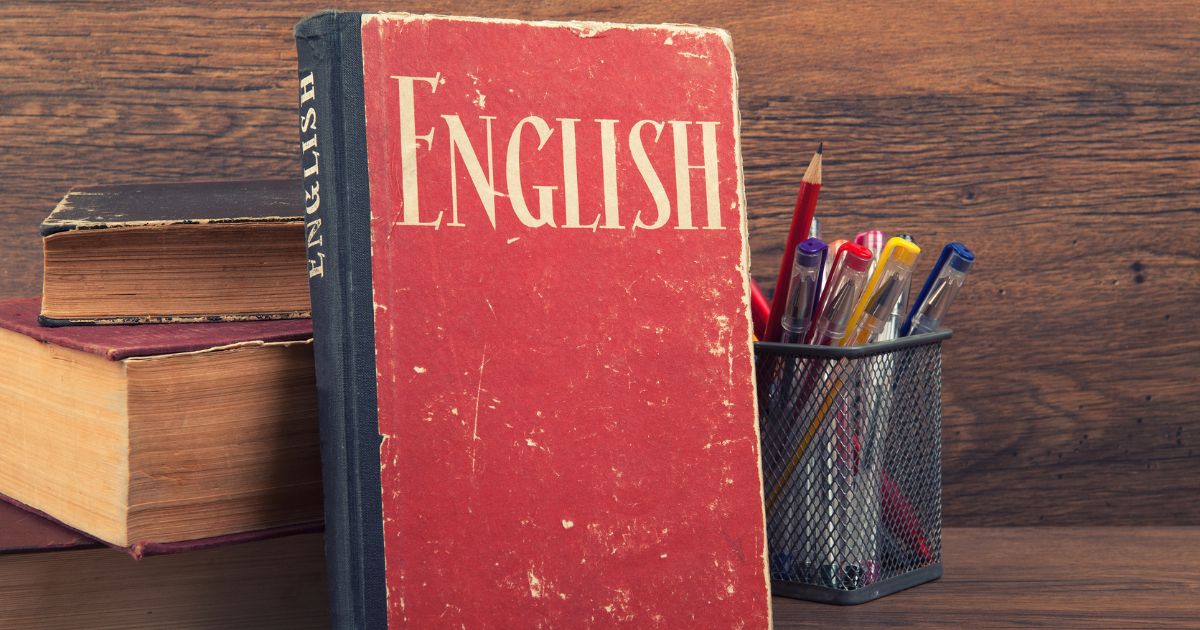IELTSのライティングタスク2で高得点を狙うためには、正確な語彙の使用が不可欠です。このガイドでは、上級者でも間違えやすい動詞について詳しく解説します。英語学習者がよく混同する動詞の使い方や、正しい使い方を具体例を交えて紹介します。
let/allow
「let」と「allow」は上級者でも間違えやすい動詞です。どちらも「許可する」という意味を持ちますが、使い分けに注意が必要です。
- 基本的な意味
- let: (したいように)させる
- allow: 許可する
「let」は「(したいように)させる、止めはしない」というのが本来の意味です。例えば、以下のように使われます。
- letの使用例
- The mentor let the interns experiment with different approaches to solve the problem independently.
- 指導者はインターンが問題を解決するために様々なアプローチを試すことを許可しました。
- The teacher let the students explore the topic without imposing restrictions.
- 先生は生徒たちに制限を加えずにトピックを探求させました。
一方、「allow」は「許可する」という意味が含まれます。例えば、以下のように使われます。
- allowの使用例
- The university allows students to access online resources even after graduation.
- 大学は卒業後も学生がオンラインリソースにアクセスできるようにしています。
- The policy allows researchers to collaborate across disciplines.
- その政策は研究者が学際的に協力することを許可しています。
このように、「let」は「(したいように)させる」という意味が強く、時には「できればしてほしくないが・・・」という含みを持つこともあります。一方、「allow」は許可のニュアンスが強くなります。このようなニュアンスの違いから、エッセイでは主に「allow」のほうを使うことが多い印象です。
rise/raise
「rise」と「raise」もよく混同される動詞です。
- 基本的な意味
- rise: <<自動詞>> 上がる
- raise: <<他動詞>> (何かを)上げる
「rise」は自動詞で、何かが(自らの力で)上がることを意味します。自動詞なので目的語を取ることができません。例えば、以下のように使われます。
- riseの使用例
- The global temperature continues to rise due to the accumulation of greenhouse gases.
- 温室効果ガスの蓄積により、地球全体の気温が上昇し続けています。
- As inflation rises, the purchasing power of the average citizen decreases.
- インフレが上昇すると、一般市民の購買力が低下します。
一方、「raise」は他動詞で、何かを上げることを意味します。他動詞なので必ず目的語が必要です。例えば、以下のように使われます。
- raiseの使用例
- The government raised the minimum wage to address income inequality.
- 政府は最低賃金を引き上げ、所得格差に対処しました。
- Researchers raised concerns about the long-term effects of the new technology.
- 研究者たちは新技術の長期的影響について懸念を表明しました。
このように、「rise」は自らの力で上がることを意味し、「raise」は何かを上げることを意味します。エッセイやスピーチでは、文脈に応じて適切な動詞を選ぶことが重要です。
admit/recognise
「admit」と「recognise」もよく混同される動詞です。特に受動態でよく間違いを見受けます。
- 基本的な意味
- admit: (特に不快な事実や過ちを)しぶしぶ認める
- recognise: (特に公式に)認識する、認める
「admit」は、特に不快な事実や過ちをしぶしぶ認めるというニュアンス意味です。例えば、以下のように使われます。
- admitの使用例
- The scientist admitted that the initial hypothesis was flawed.
- その科学者は、最初の仮説に欠陥があることを認めました。
- The politician admitted to the shortcomings of the policy during the debate.
- その政治家は討論中に政策の欠点を認めました。
一方、「recognise」は、特に公式に認識することや認めることを意味します。例えば、以下のように使われます。
- recogniseの使用例
- The academic community recognised the researcher's groundbreaking contributions to quantum physics.
- 学術界は、その研究者の量子物理学への画期的な貢献を認めました。
- It is widely recognised that critical thinking skills are essential for academic success.
- 批判的思考力が学業の成功に不可欠であることは広く認識されています。
使い分けのポイント
まとめると、
- admit: 不快な事実や過ちをしぶしぶ認める(confess に近いニュアンス)
- recognise: 正式に・客観的に認識する、承認する(acknowledge に近い)
「admit」は主に過ちや否定的な内容に対して使われ、「recognise」は功績や状況などを公式に認める場面で使われます。"She was admitted for her achievements." のような表現は不自然なので注意しましょう。
try/attempt
「try」と「attempt」もよく混同される動詞です。
- 基本的な意味
- try: (結果を気にせずに、とりあえず)やってみる
- attempt: (特に難しいことに対して、結果を出すことを目標に)試す
「try」は、一般的に何かを試みることを意味しますが、「attempt」に比べて、軽い気持ちでとりあえずやってみるというニュアンスが強いです。例えば、以下のように使われます。
- tryの使用例
- She tried to learn a new language during her free time.
- 彼女は自由時間に新しい言語を学ぼうとしました。
- They tried different methods to solve the problem.
- 彼らは問題を解決するためにさまざまな方法を試みました。
一方、「attempt」は、特に難しいことに対して(時にはしっかり計画を立てて)試みることを意味します。例えば、以下のように使われます。
- attemptの使用例
- The scientists attempted to develop a vaccine within a remarkably short timeframe.
- 科学者たちは驚くほど短期間でワクチンを開発しようと試みました。
- The institution attempted to implement a new policy to reduce carbon emissions by 50%.
- その機関は炭素排出量を50%削減するための新しい政策を実施しようと試みました。
使い分けのポイント
まとめると、
- try: カジュアルに「やってみる」(軽い試み)
- attempt: 真剣に「挑戦する」(困難な試み)
アカデミックなライティングやフォーマルな場面では、「attempt」のほうが適切な場合が多いです。
facilitate/enable
「facilitate」と「enable」はどちらも「可能にする」という意味を持ちますが、ニュアンスと使い方に違いがあります。
- 基本的な意味
- facilitate: 容易にする、促進する
- enable: 可能にする、できるようにする
「facilitate」は、すでにある程度可能なことをより容易に、スムーズにするという意味です。例えば、以下のように使われます。
- facilitateの使用例
- Online platforms facilitate communication between students and teachers.
- オンラインプラットフォームは生徒と教師のコミュニケーションを促進します。
- Technology facilitates the sharing of information across borders.
- テクノロジーは国境を越えた情報の共有を容易にします。
一方、「enable」は、それまで不可能だったことを可能にするという意味です。例えば、以下のように使われます。
- enableの使用例
- The internet enables people to work remotely from anywhere in the world.
- インターネットは人々が世界中のどこからでもリモートで働くことを可能にします。
- Advanced medical technology enables doctors to detect diseases at an early stage.
- 高度な医療技術は医師が病気を早期に発見することを可能にします。
使い分けのポイント
まとめると、
- facilitate: 既に可能なことをより簡単に・スムーズにする
- enable: 不可能だったことを可能にする
エッセイでは、状況に応じてこのニュアンスの違いを意識することが重要です。
promote/encourage
「promote」と「encourage」はどちらも「促進する」「奨励する」という意味を持ちますが、使い方とニュアンスに違いがあります。
- 基本的な意味
- promote: 促進する、推進する(組織的・公式的)
- encourage: 励ます、奨励する(個人的・精神的)
「promote」は、組織や制度として何かを推進・促進するという意味です。例えば、以下のように使われます。
- promoteの使用例
- The government launched campaigns to promote healthy lifestyles.
- 政府は健康的なライフスタイルを促進するためのキャンペーンを開始しました。
- Educational institutions should promote critical thinking skills.
- 教育機関は批判的思考力を促進すべきです。
一方、「encourage」は、個人や集団を励まし、やる気を起こさせるという意味です。例えば、以下のように使われます。
- encourageの使用例
- Teachers should encourage students to ask questions.
- 教師は生徒が質問をするよう奨励すべきです。
- Parents encourage their children to pursue their interests.
- 親は子どもたちに興味のあることを追求するよう励まします。
使い分けのポイント
まとめると、
- promote: 組織的・公式的に促進する
- encourage: 個人的・精神的に励ます・奨励する
アカデミックライティングでは、政策や制度について述べる場合は「promote」、個人の行動について述べる場合は「encourage」を使うことが多いです。
prevent/avoid/hinder
「prevent」「avoid」「hinder」は、いずれも「妨げる」「回避する」といった意味で使われることがありますが、ニュアンスや使い方が異なります。特に、エッセイやレポートでの正確な使い分けが重要です。
- 基本的な意味
- prevent: (未然に)防ぐ、起こらないようにする
- avoid: (意図的に)避ける、回避する
- hinder: (進行や発展を)妨げる、遅らせる
「prevent」は、何かが起こるのを事前に阻止する意味で使われます。たとえば以下のように使われます。
- preventの使用例
- Vaccination prevents the spread of infectious diseases.
- 予防接種は感染症の拡大を防ぎます。
- Security measures were implemented to prevent data breaches.
- セキュリティ対策が導入され、データ漏洩が防がれました。
「avoid」は、意識的にその状況に近づかないようにする行動を表します。たとえば以下のように使われます。
- avoidの使用例
- She avoids using plastic bags to reduce environmental impact.
- 彼女は環境への影響を減らすためにビニール袋の使用を避けています。
- To stay healthy, it's important to avoid processed foods.
- 健康を維持するには、加工食品を避けることが重要です。
一方、「hinder」は何かの進行・発展・成果を妨げる、遅らせるという意味で使われます。以下のように使用されます。
- hinderの使用例
- Poor internet connectivity hindered the completion of the online course.
- インターネット接続の不良が、オンラインコースの完了を妨げました。
- Lack of funding hinders scientific research.
- 資金不足が科学研究を妨げています。
使い分けのポイント
まとめると、
- prevent: 何かが「起きる前」に阻止
- avoid: 自分の行動で「避けて通る」
- hinder: すでに始まっているものの「進行を邪魔する」
それぞれ文脈や目的語によって使い方が大きく異なるため、正確に選びたい語句です。
discourage/deter
「discourage」と「deter」はどちらも「やる気をなくさせる」「思いとどまらせる」という意味を持ちますが、ニュアンスと使い方に違いがあります。
- 基本的な意味
- discourage: (気持ち的に)やる気をそぐ、やめさせる
- deter: (行動の結果や罰などにより)抑止する、思いとどまらせる
「discourage」は、精神的なやる気をくじくニュアンスが強いです。例えば、以下のように使われます。
- discourageの使用例
- Negative feedback can discourage students from participating in class.
- 否定的なフィードバックは、生徒が授業に参加する意欲をくじくことがあります。
- High tuition fees may discourage low-income families from pursuing higher education.
- 高額な授業料は、低所得層の家庭が高等教育を目指す意欲をそぐかもしれません。
一方、「deter」は、恐れや不利益を感じさせることで実際の行動を抑止するニュアンスです。
- deterの使用例
- Strict penalties are intended to deter people from committing crimes.
- 厳しい罰則は人々が犯罪を犯すのを思いとどまらせるためのものです。
- The presence of security cameras deters theft in public places.
- 防犯カメラの存在は公共の場での盗難を抑止します。
使い分けのポイント
まとめると、
- discourage: 気持ちをくじいてやめさせる(心理的)
- deter: 恐れや罰によって行動をやめさせる(抑止力)
エッセイや議論文では、状況に応じてこのニュアンスの違いを意識することが重要です。
claim/argue
「claim」と「argue」は、どちらも「主張する」と訳されるため混同されがちですが、学術的な文脈では意味とニュアンスに明確な違いがあります。
- 基本的な意味
- claim: 主張する(根拠が弱い場合も含む)
- argue: (根拠や論理をもって)論じる、主張する
「claim」は、証拠の有無に関わらず、自分の意見や立場を述べることに使われます。例えば、以下のように使われます。
- claimの使用例
- Some people claim that video games cause violence.
- 一部の人々は、テレビゲームが暴力を引き起こすと主張しています。
- The company claimed its product was 100% eco-friendly.
- その企業は自社製品が100%環境に優しいと主張しました。
一方、「argue」は、理由や根拠を示しながら論理的に主張する際に使われます。エッセイやスピーチでは好まれる表現です。
- argueの使用例
- The researcher argues that early education plays a crucial role in brain development.
- その研究者は、幼児教育が脳の発達に重要な役割を果たすと論じています。
- Many scholars argue that climate change is the result of human activities.
- 多くの学者は気候変動が人間の活動によるものであると論じています。
使い分けのポイント
まとめると、
- claim: 証拠の有無を問わず主張する(場合によっては根拠が曖昧)
- argue: 論拠をもとに理論立てて主張する(説得力のある主張)
アカデミックライティングでは、単に「claim」するだけでなく、「argue」して論理的な展開を示すことが求められます。
affect/influence/impact
「affect」「influence」「impact」はいずれも「影響を与える」という意味を持つ語ですが、使う場面や文法上の扱いが異なるため、注意が必要です。
- 基本的な意味
- affect: 動詞 / 直接的に作用する、影響を及ぼす
- influence: 名詞・動詞 / 間接的に影響を与える
- impact: 名詞中心(動詞としても使用可)/ 強い影響・衝撃
「affect」は他動詞で、直接的に作用する意味合いがあります。フォーマルな書き言葉でよく使われます。
- affectの使用例
- Climate change affects agricultural productivity.
- 気候変動は農業の生産性に影響を与えます。
- Stress can negatively affect mental health.
- ストレスは精神的健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
「influence」は、名詞と動詞の両方で使えます。影響はより間接的・長期的なものを指すことが多いです。
- influenceの使用例
- Parents significantly influence their children's values.
- 親は子どもの価値観に大きな影響を与えます。
- Social media has a strong influence on public opinion.
- ソーシャルメディアは世論に強い影響力を持っています。
「impact」はもともと名詞中心で、変化を引き起こすほどの強い影響・衝撃を意味します。動詞として使う場合はややフォーマルでビジネス寄りです。
- impactの使用例
- The new policy had a significant impact on small businesses.
- その新しい政策は中小企業に大きな影響を与えました。
- Technological advances impacted the way people communicate.
- 技術革新は人々のコミュニケーションの仕方に影響を与えました。
使い分けのポイント
まとめると、
- affect: 直接的な影響(他動詞としてのみ)
- influence: 間接的・長期的な影響(名詞・動詞両方)
- impact: 強い影響や衝撃(名詞中心/動詞も可)
ライティングでは、場面に応じて語の強さ・品詞・文構造に気をつけながら使い分けましょう。
Ask the Expert
プラスワンポイントでは、IELTS学習に関する疑問やお悩みを相談できる『無料IELTS学習相談』を実施しています。IELTSの学習方法やスコアアップのコツ、勉強計画の立て方などを、経験豊富なカウンセラーが無料でアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。
- 試験を何回受けてもスコアがなかなか上がらない
- 自分自身の学習方法が正しいかどうかを知りたい
- 学習・受講プランの相談に乗ってもらいたい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人
Hibiki Takahashi
日本語で学ぶIELTS対策専門スクール 『PlusOnePoint(プラスワンポイント)』創設者・代表。『英語ライティングの鬼100則』(明日香出版社)著者。1997年に大阪大学医学部を卒業後、麻酔科専門医として活躍。2012年渡豪時に自身が苦労をした経験から、日本人を対象に IELTS対策のサービスを複数展開。難しい文法・語彙を駆使するのではなく、シンプルな表現とアイデアで論理性・明瞭性のあるライティングを指導している。これまでの利用者は4,500名を超え、Twitterで実施した「12週間チャレンジ」では、わずか4週間で7.0、7週間で7.5など、参加者4名全員が短期間でライティングスコア7.0以上を達成(うち2名は7.5を達成)。「IELTSライティングの鬼」の異名を持つ。オーストラリア在住14年、IELTS 8.5(ライティング 8.0)、CEFR C2。
あわせて読みたい記事

ライティングサミット 第183週モデルアンサ...
2025年12月21日更新
ライティングサミット
ライティングサミット受講生限定コンテンツです。閲覧にはライティングサミット受講生の権限が必要です。...
記事を読む

事前の準備が勝敗を分ける|プランニングのプロ...
2025年11月16日更新
ライティング・タスク2
プランニングのプロセスを解説します。IELTSライティング・タスク2では、アイデアを事前に整理して、論理的に説明する力が求められるため、事前のプランニングが非常...
記事を読む

IELTSを勉強するならまずこれを読むべし!...
2021年8月20日更新
紹介記事
と偉そうなタイトルを付けましたが、私のIELTS解説ではなく他力本願な内容です。コロナ禍でオーストラリアの国境は閉じていますが、だからこそ「今のうちにIELTS...
記事を読む

number と amount の使い分け...
2025年11月27日更新
ライティング・タスク2
IELTSライティングでよく見られる「number」と「amount」の誤用について解説します。可算名詞・不可算名詞の違いを理解し、適切に使い分けることで、より...
記事を読む

IELTSライティング7.0|PlusOne...
2020年8月22日更新
紹介記事
前回のブログでIELTSライティング7.0を独学で取得した勉強法についてシェアしました。正しい方向に向って努力すれば独学で7.0は不可能ではありませんが、簡単な...
記事を読む
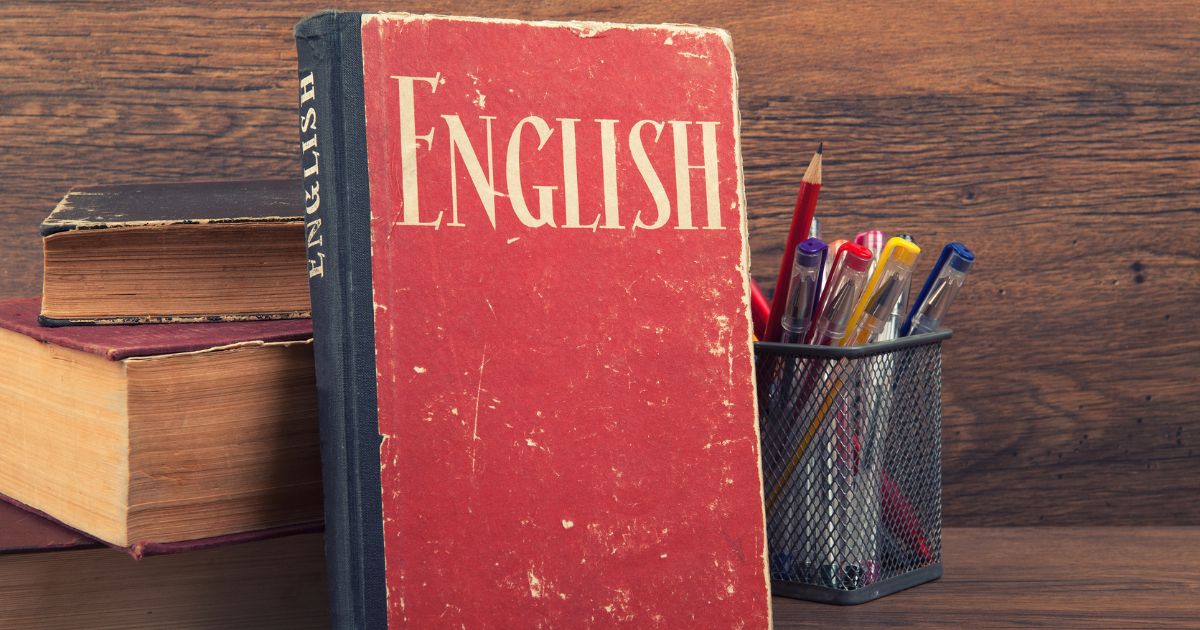
let vs allow...
2025年11月25日更新
語彙・表現
letとallowは、どちらも「許可する」を意味しますが、使用場面やニュアンスに重要な違いがあります。この記事では、両者の使い分けを具体例とともに詳しく解説しま...
記事を読む