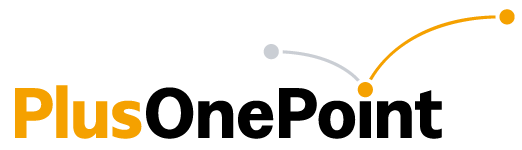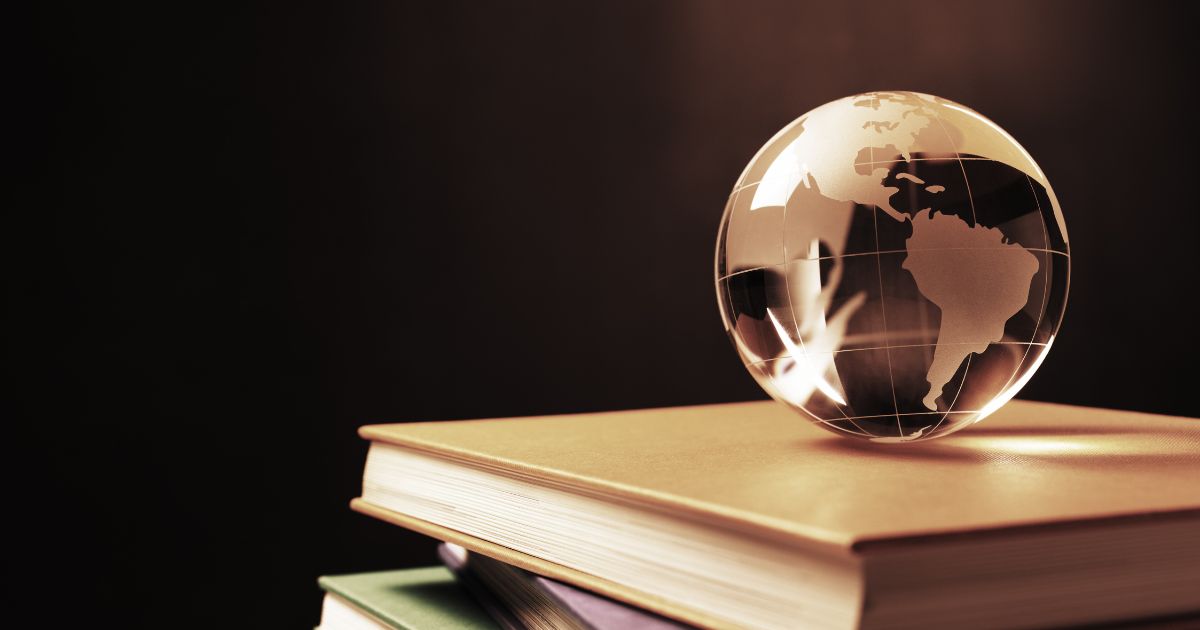IELTSライティング・タスク2では、自分にとってあまり馴染みのない概念が出題されることがあります。皆さんは、「ソーシャルバリュー」という言葉を聞いたことがありますか?
実は、ILETSライティングでは、このような社会的なテーマについてのエッセイを書くことが求められることがあります。今週のライティングサミットではちょうどこのテーマを扱っていますので、今回は、ソーシャルバリューについて解説します。
ソーシャルバリューとは?
まずは以下のタスクをみてみましょう。
- Task
- Nowadays, most countries can improve the standard of living through economic development, but some social values are lost as a result. Do you think the advantages of this phenomenon outweigh the disadvantages?
- 現在、ほとんどの国は経済発展を通じて生活水準を向上させることができますが、その結果、いくつかの社会的価値が失われています。 この現象の利点が欠点を上回ると思いますか?
このタスクは、ライティングサミット第145週で取り上げられました。
多くの方が「ソーシャルバリュー」という言葉に戸惑うことでしょう。しかし、皆さんだけではありません。ライティングサミットの受講生の方も、このワードに戸惑った人も多くおられました。
今回の記事では、「ソーシャルバリュー」という概念について掘り下げてみましょう。
ソーシャルバリューとは?
ソーシャルバリューは、日本語は「社会的価値(または価値観)」あるいは「社会的規範」などと訳されます。
社会の中で多くの人々が大切だと考える行動の基準や信念、道徳的な考え方のことを指します。これは単なる個人の価値観ではなく、「社会全体としてこうあるべき」とされる共通認識のようなものです。
例えば、以下のようなものが「社会的価値」に相当します。
- 社会的価値の一例
- 家族とのつながりを大切にすること
- 他人に対して親切であること
- 地域社会で助け合いをすること(共同体意識)
- 高齢者へ敬意を払うこと
- 世代間のつながりを大切にすること
- 公共の場でのマナーを守ること
- 環境に配慮した行動をすること
- 公共の福祉に貢献すること
分かりやすくいうならば、昭和の時代には当たり前であったことで、今の時代には薄れてしまった価値観を想像するといいかもしれません。
経済発展を優先するあまりこのような社会的価値が失われるという欠点を、経済発展によって得られる利点と比較して考えるというのが、このタスクの趣旨です。出題者の意図としては、経済発展によって生活は便利で豊かになる一方で、人々の心のあり方や他人とのつながり、社会に対する責任感といった目に見えない価値が後回しにされることがあるが本当にそれでいいのか、という問題提起でしょう。
経済至上主義とソーシャルバリュー
「経済至上主義」とは、経済的な成長や利益を最優先し、経済的な豊かさが社会の幸福や成功を測る基準であるとする考え方です。現代社会においては、GDP(国内総生産)の成長率や企業の収益性ばかりが注目され、数値で表しにくい社会的な価値観や道徳的な基準が軽視される傾向があります。
例えば、多くの企業では売上や利益の向上を求めて、従業員に過度な長時間労働や過密スケジュールを強いることがあります。日本の労働環境では特にこうした傾向が顕著であり、経済成長期以降、「過労死」や「メンタルヘルスの悪化」など深刻な社会問題を引き起こしています。仕事に追われて家族とのコミュニケーションが減り、子どもや高齢者との時間を十分に確保できなくなる家庭も少なくありません。
また、経済効率を追求するあまり、地方のコミュニティが弱体化する事例も見られます。日本各地の商店街が、大型ショッピングセンターやオンライン通販の台頭によって衰退し、かつて地域住民が自然に交流していた場が失われています。この結果、人々が互いを助け合う機会が減り、高齢者の孤立化が進んでしまうという問題にもつながっています。
さらに、効率性重視の考え方が公共サービスにまで及ぶと、社会的に弱い立場の人々への配慮が軽視される恐れがあります。例えば、高齢者や障害を持つ方々が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、行政の細かなケアや地域の助け合いが必要ですが、経済的合理性だけを追求すると、こうしたサービスはコストが高いとして削減される可能性があります。
このように、経済至上主義が過度に進行することは、社会の調和や人間同士のつながりを損ない、結果として人々が真に幸福や豊かさを感じにくい社会を生み出す可能性があります。私たちは、経済的な豊かさと社会的な価値観のバランスをどのように取っていくのか、改めて考える必要があるのではないか、と出題者は受験生に問いかけているのでしょう。
- 経済至上主義により失われやすい社会的価値
- 家族や地域とのつながり(過労による時間不足)
- 地域コミュニティの連帯感(商店街の衰退など)
- 社会的弱者への配慮(効率性優先によるサービス削減)
グローバリズムとソーシャルバリュー
グローバリズム(グローバル化)とは、人・物・情報が国境を越えて自由に移動し、世界が一体化していく現象を指します。近年、私たちの生活はますますグローバル化の影響を受け、海外の商品を簡単に購入できたり、SNSを通じて外国の人々と簡単に交流できたりするようになりました。このようにグローバル化は経済面や文化交流の活発化をもたらしますが、一方で、各国や地域が長年培ってきた社会的価値観や伝統を揺るがすことにもつながっています。
例えば、世界的に広まっている欧米の個人主義的価値観や消費文化の影響を考えてみましょう。もともと日本をはじめとするアジアの国々では、家族や地域の共同体とのつながりを非常に重要視する傾向がありました。しかしグローバリズムの進展とともに、個人の自由や自己実現を重視する西洋的価値観が若い世代を中心に広まっています。その結果、核家族化や単身世帯が増加し、伝統的な家族観や地域コミュニティの連帯感が徐々に薄れつつあります。
具体的には、日本では近年、「町内会」や「自治会」といった地域コミュニティへの加入率が減少しています。グローバル化がもたらすライフスタイルの多様化や個人主義的な考え方の浸透により、地域社会の活動を「煩わしい」「個人の自由を制限する」と感じる人が増えていることが原因の一つと言われています。
また、文化的な側面でもグローバルスタンダードが広まることで、各地の伝統行事や習慣が衰退する傾向にあります。例えば、日本の伝統的な年中行事や祭りが若い世代の関心を失い、廃れてしまうケースが増えているほか、地方の伝統工芸や職人文化も後継者不足に悩まされています。これは世界各地でも同様に起きており、世界共通の「便利さ」や「経済効率」を求めるあまり、固有の文化や社会規範が次第に軽視される傾向にあるのです。
もちろん、グローバル化によって経済が活性化し、物質的な豊かさや生活の利便性が向上すること自体は喜ばしいことでしょう。しかし、こうした利便性や経済的利益を享受しつつも、自国や地域が持つ独自の社会的価値や文化をどのように保護し、未来へと継承していくべきかは重要な問題です。このような内容を問う問題も、IELTSライティングでは出題されていますので合わせてチェックをしておきましょう。
- グローバル化の影響
- 個人主義的価値観が浸透し、共同体意識が低下
- 伝統行事や文化への関心が薄れる
- 地域固有の習慣や工芸が後継者不足に
現代の政治とソーシャルバリュー
近年、多くの国で伝統的な社会的価値を重視する政治的な動きが見られます。これらは、グローバル化や経済至上主義の進展により失われつつある地域の文化や共同体意識を取り戻そうとする試みと言えるでしょう。
例えば、一部の国では自国産業の保護や移民政策の見直しなど、自国の雇用や文化を優先する政策が実施されています。これらの政策は、経済のグローバル化によって自国の製造業が衰退し、地域経済が弱体化することへの懸念から生まれています。
また、伝統的な家族観やコミュニティの価値観を重視する政策も議論されています。一方で、こうした動きは多様性や個人の権利を重視する立場からは批判を受けることもあり、社会的な議論を呼んでいます。
このように、グローバル化と地域文化の保護、経済発展と伝統的価値の維持というバランスをどのように取るかは、現代社会が直面する重要な課題の一つです。IELTSライティングでは、こうした複雑な社会問題について、客観的かつ論理的に自分の意見を述べる力が求められます。
まとめ
今回の記事では「ソーシャルバリュー」という概念について解説しました。IELTSライティングでは、このような社会的なテーマについてのエッセイを書くことが求められることがありますので、しっかりと理解しておくことが重要です。
経済的利益を追求するあまり、地域社会や家族関係が弱体化するケースや、グローバルスタンダードによって伝統や文化が薄れる現象など、多くの課題があります。IELTSライティングを通じて、このような現代社会の抱える複雑な問題を考察し、自分自身の意見を論理的に構築できる力を養っていきましょう。
Ask the Expert
プラスワンポイントでは、IELTS学習に関する疑問やお悩みを相談できる『無料IELTS学習相談』を実施しています。IELTSの学習方法やスコアアップのコツ、勉強計画の立て方などを、経験豊富なカウンセラーが無料でアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。
- 試験を何回受けてもスコアがなかなか上がらない
- 自分自身の学習方法が正しいかどうかを知りたい
- 学習・受講プランの相談に乗ってもらいたい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人
Hibiki Takahashi
日本語で学ぶIELTS対策専門スクール 『PlusOnePoint(プラスワンポイント)』創設者・代表。『英語ライティングの鬼100則』(明日香出版社)著者。1997年に大阪大学医学部を卒業後、麻酔科専門医として活躍。2012年渡豪時に自身が苦労をした経験から、日本人を対象に IELTS対策のサービスを複数展開。難しい文法・語彙を駆使するのではなく、シンプルな表現とアイデアで論理性・明瞭性のあるライティングを指導している。これまでの利用者は4,500名を超え、Twitterで実施した「12週間チャレンジ」では、わずか4週間で7.0、7週間で7.5など、参加者4名全員が短期間でライティングスコア7.0以上を達成(うち2名は7.5を達成)。「IELTSライティングの鬼」の異名を持つ。オーストラリア在住14年、IELTS 8.5(ライティング 8.0)、CEFR C2。
あわせて読みたい記事

アイデアは問われないのは本当か?...
2025年12月4日更新
ライティング・タスク2
IELTSライティング・タスク2では事実の正確性は問われませんが、論理的整合性は厳しく評価されます。事実認識の誤りと論理的矛盾の違いを理解し、説得力のある議論を...
記事を読む

ライティングサミット 第183週モデルアンサ...
2025年12月21日更新
ライティングサミット
ライティングサミット受講生限定コンテンツです。閲覧にはライティングサミット受講生の権限が必要です。...
記事を読む
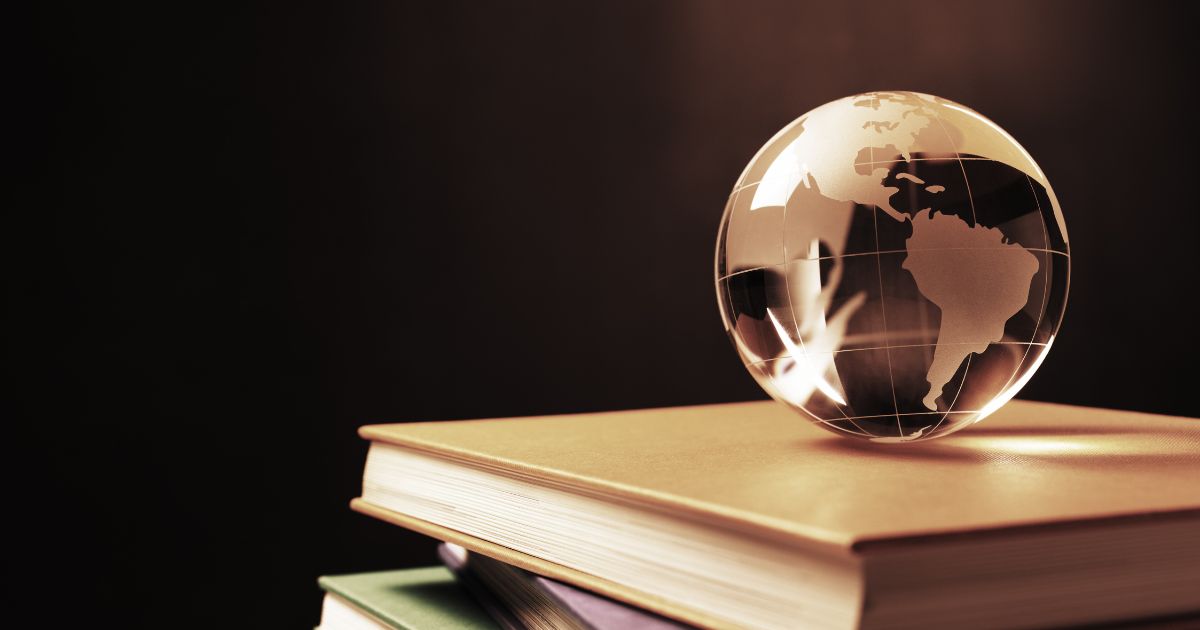
【2025年完全保存版】IELTSリスニング...
2025年1月1日更新
【完全保存版】IELTS総合対策
英語のリスニングは、日本人が英語学習をしていく上で苦手とされていることの一つです。特にIELTSのリスニングは一度しか音声が流されないために、本番で自身の実力を...
記事を読む

ライティングサミット 第182週モデルアンサ...
2025年12月13日更新
ライティングサミット
ライティングサミット受講生限定コンテンツです。閲覧にはライティングサミット受講生の権限が必要です。...
記事を読む

IELTSライティング|独学で7.0を取得し...
2020年8月15日更新
紹介記事
こんにちは、Mari(@Mari_Nurse_SA)です。IELTSのライティングは、多くの受験者が苦労するセクションです。私も例外なくライティングに悩まされ最...
記事を読む
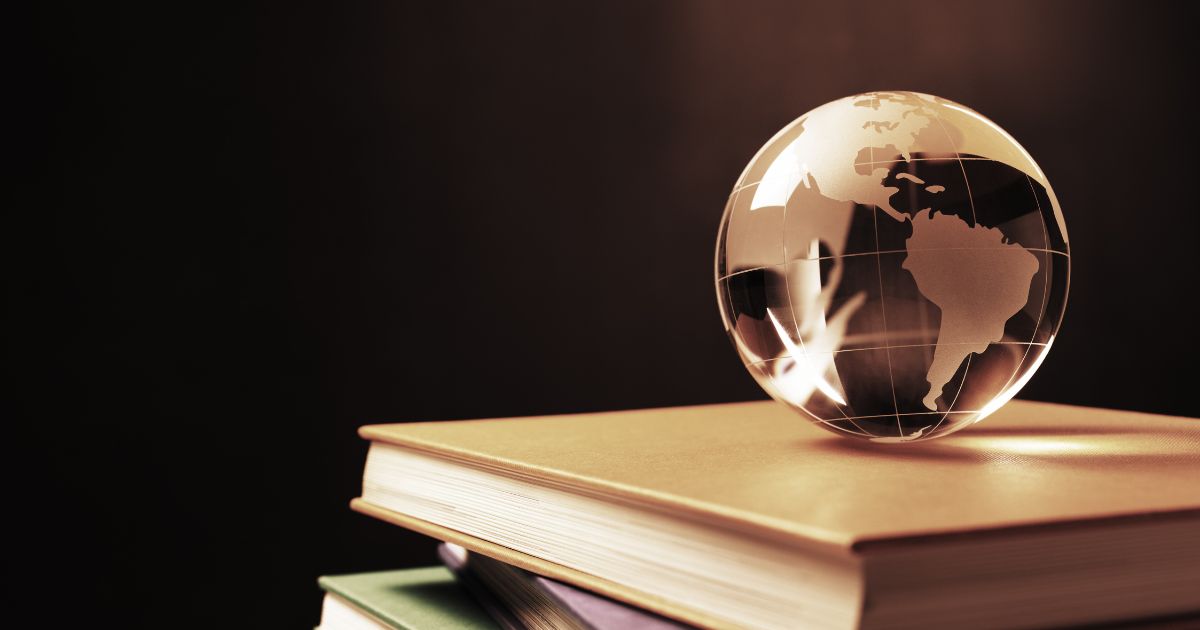
【2025年完全保存版】IELTSスピーキン...
2025年1月1日更新
【完全保存版】IELTS総合対策
IELTSのスピーキングはひとりで練習することが難しく、またスコアの採点基準について日本語での正確な情報が少ないことから、対策が難しいと感じている方も多いようで...
記事を読む