この記事を書いた人
Rui Atsue
プラスワンポイントの創業メンバーであるMika先生とともに、日々IELTS対策記事や動画の制作に力を入れています。最新のトレンドや効果的な学習法を読者にわかりやすく伝えることを心掛け、学生や社会人問わず、多くの受験者に貢献してきました。現在は、ニュースレターの編集をメインに担当し、読者が常に新鮮な情報を得られるよう努めています。受験者一人ひとりの目標に寄り添い、実現に向けてサポートしています。
ニュースレター過去配信記事
語彙強化方法★その2
〜実践ベースで単語を覚える!〜
2024-11-18
こんにちは^^
プラスワンポイントのルイです!
今日もIELTS学習、がんばって取り組んでいますでしょうか?
ちょっと前回から時間が空いてしまいましたね。今年は秋の訪れが遅く、先月はいつまでも残暑を引きずっていたような気候でしたが、日本ではそろそろ寒さを感じるようになってきたのではないでしょうか?
すでに11月の後半!もう来月にはクリスマス、あっという間にお正月が来ますので、年末、1月後半をめどに目標を立てている方は追い込み時期ですね^^
時間は有限ですが、何事も焦りは禁物です。いつもどおり、たんたんと、課題をこなしていきましょう!
今回は前回の続きで、リーディングのための語彙強化方法その2、実践ベースの語彙強化方法をお伝えしていきます!
★ 学習方法は、学習者の状況により最適解が異なる
★ 単語力がなくて読めません!その1(前回)
★ 単語力がなくて読めません!その2〜実践による語彙力強化編〜(本日のトピック)
★ 読むのが遅くて困ってます><< /p>
★ 日本語の参考書 vs Cambridge公式問題集
★ 2周目以降を解く意味とは?
この方法は、「実践ベース」という呼び方そのままではありますが、基本的には実際に問題を解く、英語の文章を読む(聞く)ことで語彙を増やしていくという方法です。
そうはいっても、もちろんそれなりに方法や注意点はあります。ただ読んだり聞いたりしているだけで自然と増えていく語彙もありますが、「語彙強化」のために行うという目的意識をもって工夫をすることで、「自然に」以上の効果が期待できるということです。
詳しいやり方はまた別項で紹介しますが、単純暗記作業やドリル的練習方法よりも、読むことや、情報を得ること、実際に問題を読んで解決することが好きな人に向いている学習方法と言えます。
また、単語の暗記学習が嫌いな人が「単語力がないから英語ができない」と思い込んで英語を嫌いになったりしないための提案でもあります。単語を先に揃えておかないとIELTSができないわけではないんです。読みながら、解きながら覚えていく方法でも学習を進めることはできるのですね。
前回もお話ししたように、英語の学習にはどうしてもこの方法でやらなければならないということはありません。日本では学校で単語テストを採用しているので単語暗記学習が重視され、大変人気のある学習方法ではありますが、IELTSには単語テストはありませんので、別の方法でも語彙強化はできるのです。
さて、この実践ベースの語彙強化方法にはどんな利点欠点があるのか見ていきましょう。
まずは、記憶に残りやすい点です。
コンテクストの中で意味を理解しながら覚えていくため、単語の意味だけでなく、書かれている情報、内容そのものが記憶に残ってくれます。長期記憶には、エピソード記憶というものがありますが、実践という体験、内容を理解する経験、または内容そのもののエピソード性が記憶と結びつくため、思い出すためのトリガー的要素が多いのですね。
次に、訳語ではなく、単語のイメージを感覚として捉えやすいという点があります。実践ベースで単語を覚えるということは、
こういう状況の時に、この語を使うんだ
というように、訳語からではなく、その単語が必要となる状況から、意味の理解が導かれます。
英単語は日本語訳がなければ覚えられないわけではありません。むしろ和訳(やそのイメージ)が固定され、より本質的な英単語の意味や感覚的理解を妨げることもあるくらいです。「英単語=訳語」のイメージが固まってしまうと、意味が状況と一致しない場合に混乱が起きることがあります。
例えば、”ground”という単語があります。ほとんどの人が「地面」または「グラウンド(運動場)」という訳語で最初に覚えるのではないでしょうか?
次の例文を「地面」という訳語しか知らない前提で、読み進めてください。
Snow covered the ground completely by morning.
朝までに雪が「地面」を完全に覆っていた。
"ground"のイメージも意味もそのままですので特に違和感はないですね?
では次の例文を見てください。
There is no solid ground for his argument.
彼の議論には「固い地面」がない?
意味が状況と一致しませんね。このような文に出会うと、この"ground"は「地面」ではなさそうだけれど、全く意味が分からず混乱します。

もう一つ、次の例文を見てみましょう。
Learning grammar is the ground for mastering any language.
文法を学ぶことは、どの言語を習得するにしても、〇〇だ。
この"ground"も「地面」ではなさそうだけど、文脈からなんとなく意味がわかりそうな気がします。
この"ground"は、「基礎」のような意味じゃないだろうか?
「基礎」のようなイメージなら、2つ目の例文「彼の議論には固い〇〇がない」にもこの当てはめることができそうです。
固い基礎?→しっかりした基盤?→根拠?
これなら意味がわかりそうですね。
There is no solid ground for his argument.
彼の議論には「しっかりした根拠」がない
そうです、この"ground"は、「根拠」や「理由」という意味になるわけです。
また、実際には、文章はこの1文だけでなく、それまでのストーリーがあります。「彼の議論(主張)にはしっかりした根拠がない」と書かれる前の経緯(いきさつ)です。そのさらに詳細な文脈を読み進めていれば、自然と、"ground"の意味をある程度想像することもできるわけですね。
→議論(主張)に〇〇がない、というからにはネガティブな意味合いだろう。
→議論(主張に)にあるべきもののことを言っているはずだ。
このような感じで、「理由」や「根拠」のようなイメージを想像するということです。
このように、それぞれの文脈で「地面」「基盤」「根拠」など、"ground"の意味が変わりますが、根幹にあるイメージに共通性があることがわかりますね。全て「物事の土台や基盤」といった意味に派生しているのです。文脈から、語源や基本イメージを意識して、「なんとなくこんなような意味」として捉えておくと、訳語に頼らず自然な文脈理解ができるようになるのです。
これが訳語に頼らない語彙学習の利点です。
これも、実践から学ぶので当然と言えば当然ですが、試験で使われている語彙・表現に嫌でも慣れていくことになります。
特にIELTSは似たテーマの出題がたくさんあり、その中で使われている必須単語は広い範囲で被ります。毎回毎回出会うことで、状況とともに意味と使われ方を覚えることができるわけです。特に、「設問で使われている表現」はかなり共通しています。そのくせ無駄に理解しにくいものとかもありますので、瞬時に理解できるくらいに慣れておけば大変有利になりますね。
例えば、
a reference to —— / an account of —— / an explanation of —— /
これはインフォメーションマッチングという問題で毎回のように見かける表現ですが、単に——についての説明・言及くらいの意味しかありません(重要なのはその後の内容)。しかし慣れていないと、ちゃんと理解するために丁寧に読んでしまうので、たくさんの時間を使わなくてはならないことになります。

また、ほぼ確実に登場する単語、とその言い換えをまとめて覚えることもできます。
例えば、実験(experiments)を行う時に使う動詞表現の言い換えには、
perform / conduct / carry out
のどれかが使われていますし、
実験の結果は、
resultのほかに、outcome / finding があります。
その問題点は、
problem やissue以外に、fault / flawもよく使われます。
IELTSでは科学、実験に関するパッセージはそれこそ毎回のように出題されていますので、問題を解くたびに、それこそ忘れる前にまた出会う、しかも言い換え表現とセットで出会うことになり、必要な語彙を速攻で覚えることができるわけです。
語学学習において辞書を引く習慣はぜひ身につけておきたいものですが、単語帳学習ではどうしても、辞書を引く機会が失われてしまいがちです(なぜなら覚えるべき訳語は決まっていてすでに書かれているから)。これが、実践ベースで語彙学習をしていると、確認のために辞書を引くことになりますので、この習慣をうまく活用できれば素晴らしい効果が得られます。
ひとつの単語には複数の意味(訳語)があります。語源やイメージが共通するものもありますが、簡単には意味が想像できない単語や、全く初めて出会う単語だってたくさんありますね。そんな時は、①いったんすっ飛ばすか、②手っ取り早く辞書を引くことになるでしょう。もしも何度も出会う単語であればそのまま放っておくわけにもいかないのでいずれ調べますね。
辞書を開くと、たくさんの情報が書いてあります。
意味をたくさん持つ単語はそれこそ、訳語もたくさんありますし、品詞としての役割も1つだけではないものもあります。同じ単語なのに使われ方によって形容詞だったり名詞だったり動詞だったりする場合もあるわけです。また、動詞であれば他動詞/自動詞の区別、使い方、一緒に使う助詞、特別な用法など様々な勉強をさせてくれます。
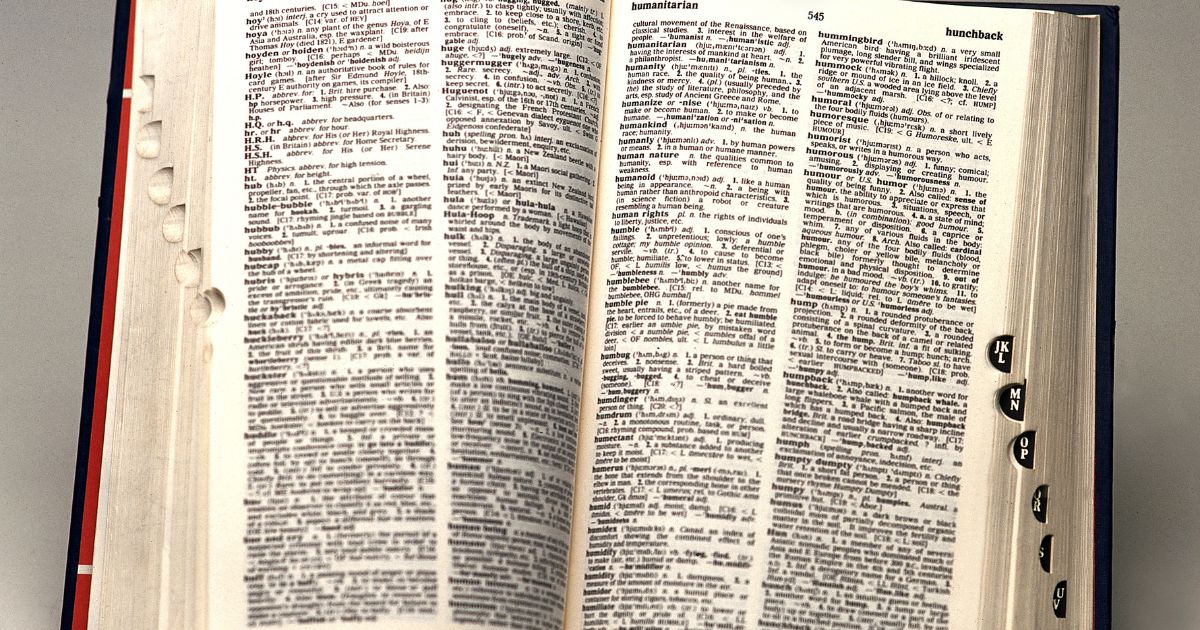
特に英文を理解する上で、品詞の働きを理解していることはとても重要です。その単語がどんな役割でその場所に置かれているのかがわかっていれば、単語の意味を知らなくても状況は想像できたりします。
これはみなさんが、中学・高校の英語の学習を通して「文法」として学んできたことですが、学校では時間の制約から体系的なルールのみで、なかなか実践までできません。実践として使う(読む・書く)場合には様々な単語が必要となりますし、基本のルールとは少し違って見えることもあります。辞書でそれぞれの単語の働きと正しい使い方を、改めて、すでに知っているルールに当てはめながら覚えることができるわけですね。
このように、辞書を引く(読む)効果は絶大なのです。
もしも、単語を調べる時についついインターネットで訳語だけ調べてしまっている方、辞書の使い方をあまり知らないという方、大変もったいないです!今の方法でうまくいっていないと感じたら、もう一度単語学習の効率を見直すために辞書と向き合ってみると良いかと思います^^
デメリットもないわけではありません。ひとつに、「まとめて〇〇単語覚える、ということはできない」ことです。学習方法の性質上当然ですね。ただ、みなさんは〇〇単語覚えることを目標に学習しているわけではありません。あくまでIELTSのスコアを伸ばすことを目指しているので、特に大きな問題にはならないでしょう。次に、「やり方に注意しないと英語初心者にはかなりしんどい」という点です。これは学習者の性格にもよりますが、調べるものが多いほど時間がかかるので、なかなか次のパッセージに進めない上にかなり疲れます。また、そもそも文章を読むのが嫌いな人にとっては結構な苦行になることでしょう。前回も言いましたが、いやいや学習したらどうしても効率は落ちます。もちろんやり方を工夫することによって継続しやすくできますが、今の自分にはどんな学習ができるのか?自分で試して選ぶことが大切です。
さて、ちょっと長くなりましたので続きは次回に持ち越します^^
次回は実際のやり方と、注意点を見ていきましょう。初心者でもやりやすい工夫も紹介する予定です。
今回もここまで読んでくださりありがとうございました!
みなさんのIELTSへの挑戦を応援しています!