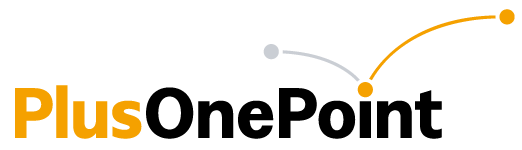【2025年完全保存版】
IELTSリスニング対策
最終更新日:2025年2月20日
英語のリスニングは、日本人が英語学習をしていく上で苦手とされていることの一つです。特にIELTSのリスニングは一度しか音声が流されないために、本番で自身の実力を出しきれないと悩む方も多いようです。
リスニング対策を行っていく上で重要なことは、英語のリスニングのスキルはもちろんのこと、問題の傾向と対策をしっかり把握・対策をしておくことです。
これらを実践することで、自身の実力を最大限発揮することができ、実力通りあるいは実力以上のスコアを狙うことができるようになります。
本記事では、そのような点も含めてIELTSリスニングの対策に役立つ情報を順番に紹介いたします。問題の傾向、スコア別の対策、本番の試験の流れなど、リスニング試験の対策にお役立ていただければ幸いです。
目次
- 01 IELTSリスニング試験の流れ
- 02 Computer-Delivered IELTS(CDI)
- 03 リスニング試験の構成
- 04 IELTSリスニングの正答数とスコア
- 05 目標スコア別の正答数の目安(パート別)
- 06 IELTSリスニングの難易度
- 07 IELTSリスニングの問題形式
- 08 基本的なリスニングの自己学習法
- 09 試験を受ける際の5つの注意点
- 10 試験前に知っておきたい3つのこと
- 11 スコアが伸びる3つのこと
- 12 まとめ
|
IELTSのリスニング試験は、アカデミックとジェネラルで同じ問題が出題されます。試験時間は35〜40分間です。
まずはじめに回答用紙が配られます。試験監督からの指示を聞きながら名前などの必要事項を記入します。ペーパー試験であれば、続いて問題(冊子)が配布されます。多くの会場ではスピーカーからオーディオが流されますが、最近ではヘッドホンを使用することが可能な会場が増えています。配布された問題の冊子は指示があるまで開くことはできません。
コンピューター試験(Computer-Delivered IELTS、以降「CDI」と呼びます)のリスニング試験では、問題の事前配布はありません。試験を始める前にサウンドチェックとして音量やヘッドホンの不具合を確認する時間が設けられていますので、その時間を有効に活用してリスニングの音量が適切であるかどうか確認しましょう。
サウンドチェックが終わったら、音声案内に従って試験が始まります。リスニングの問題はすべて1回しか聞くことができませんので、しっかり集中して聞くようにしましょう。すべての音声が流れた後、紙ベースの試験では10分間、CDIでは2分間の時間を与えられます。途中で回答用紙に答えを記入する時間がなかった場合にはこの時間に回答を埋めましょう。またスペリングミスなどをチェックする時間としても使うことができます。CDIでは、紙ベースの試験とは異なり、最後の確認時間が2分間しかないことを忘れないようにしましょう。なお、リスニング試験中の途中入退室は許められていません。
リスニング試験のサンプル問題|
前述のように、IELTS試験は従来のペーパー試験からコンピュータ試験(CDI)に変わりつつあります。CDIは、結果も早い(最短で翌日)などのメリットもありますが、デメリットもありますので、ペーパー試験とCDIを選べる方は、違いを把握した上で自分に有利な方法で受験をするといいでしょう。
2.1 CDIのメリットとデメリット
CDIのメリット
- ヘッドホンを使用できる
- 試験開始時間と同時に問題を見れる
- パートとパートの間の間隔が比較的長い
CDIの最大のメリットは、ヘッドホンを使用できる点です。
スピーカーでのリスニング試験を経験したことがある方はこのメリットを痛感できるはずです。席によって音の聞こえ方が異なる、音量の調整も自由に行うことができない、周囲の雑音で聞き取りにくくなることがある、などスピーカーでのリスニング試験は環境に左右されますが、CDIではそれらが解消されます。ただし最近ではペーパー試験でもヘッドホンを使って実施している会場が増えているため、CDIのメリットとしては少し薄れてきています。
紙ベースの試験ペーパー試験では音声案内があるまで問題を見ることができませんが、CDIでは、試験開始時間と同時にパソコンの画面に問題が表示されるため、ペーパー試験よりも少し早めに問題に目を通すことができます。わずかな時間ですが先読みがスコアに直結するリスニングでは大きなメリットになり得ます。
ペーパー試験とCDIでは、それぞれのパートの間の時間(前のパートが終了してから次のパートが始まるまでの時間)が異なります。CDIでは、ペーパー試験よりも15秒〜20秒程度と長く設定されています。パートの途中にあるインターバル(パートの前半と後半を分けるインターバル)も同様に長く設定されています。CDIでは、試験の最後に回答を書き写す時間が非常に短い(ペーパー試験では10分、CDIでは2分)ため、その分が各パートに割り当てられているものと考えられます。問題を先読みすることに使いつつ、最後に回答をチェックする時間が少ないことも考えながら回答チェックも済ませておくようにしましょう。
CDIのデメリット
- 最後の書き写し時間が短い(2分)
- 音声を聞きながらメモを取りにくい
CDIではパートとパートの間の時間が紙ベースの試験よりも長めに確保されている分、最後に回答を書き写す時間が非常に短いので注意をしましょう。ペーパー試験では最後に回答用紙に書き写す時間が10分間ありますが、CDIでは2分間しかありません。
さらにそれよりも大きなデメリットと言えるのは、音声を聞きながらメモを取りにくいことです。ペーパー試験では、問題用紙にメモを取ったりキーワードに印がつけたりすることができますが、CDIではそのようなことが難しくなります。CDIでも問題のキーワードにハイライトをつけたり、事前に渡されるペンと紙を使ってメモをとることもできますが、実際には画面上にハイライトをしたり別の紙にメモをとるような時間的余裕はないと思っておいた方が無難です。ペーパー試験に慣れている方は、普段の練習からこの点を意識しておくことが重要です。
|
リスニング試験は4つのパート(Part 1〜Part 4)で構成されています。それぞれのパートで進行のパターンはある程度決まっていますので、まずは各パートがどのようなスタイルなのかを確認しておきましょう。パート別・目標スコア別の対策については後ほど詳しく紹介します。
Part 1
スピーチの形式
2人の会話で進められます。
内容
日常生活の一場面で、電話のやり取りが多く出題されます。例えば、以下のような内容が出題されます。
- フェスティバルなどイベントの案内
- 仕事の応募
- ツアーの問い合わせ
- スポーツセンターなど施設への問合せ
問題タイプと特徴
最も難易度の低いパートです。10問全てメモなどの穴埋め問題であることが多いですが、選択問題、分類問題などとの組み合わせもあります。数字、人の名前、住所の書き取りが頻出するため、スペルの聞き取り練習などしておくといいでしょう。
近年の難易度
以前は、Part 1は初級者の得点源とされていましたが、近年はパート間の難易度の差がなくなりつつあり、Part 1の難易度は上がってきています。ただ、そうは言っても得点源にしたいパートですので、しっかり練習をしておきたいところです。公式問題集を使って練習をする方は、なるべく最新の号を使って練習をすることをおすすめします。
Part 2
スピーチの形式
1人の話し手がスピーチをします。
内容
日常生活の一場面で、1人の話者が詳細を説明したり案内したりします。例えば、以下のような内容が出題されます。
- 劇場やスポーツ施設などの案内
- 観光地などで、ガイドの説明
- 仕事の説明
問題タイプと特徴
選択問題、マッチング問題、穴埋め問題など幅広く出題されますが、問題用紙の設問は文字が少なめで簡単に見えます。ただし、一人の話者のためスピードが早く、聞き逃しやすいパートでもあります。
近年の難易度
Part 2は、Part 3と並んで難易度が高いパートです。話の流れをしっかり追うことができているかを試される問題です。特にマッチング系の問題は難しく、最新の公式問題集を使って十分に練習しておくことをおすすめします。
Part 3
スピーチの形式
2〜3人の会話形式です。
内容
大学の課題について、2〜3人で話し合う場面が多く出題されます。例えば、以下のような内容が出題されます。
- 教授からアサイメントや論文のアドバイスをうける
- 生徒同士でプレゼンテーションの内容を話し合う
- 先輩から進路やプロジェクトについてのアドバイスをもらう
問題タイプと特徴
問題の性質として、最も難易度が高いパートです。選択問題、マッチングの問題が多く出題され、問題タイプとしてはパート2と似ていますが、対話のなかで話が二転三転するため、話の内容が複雑になります。話の流れをしっかりと追い、細かな内容まで聞き取る必要があります。また、舞台が大学であるため、学術的なレポートの構成に関連する単語を覚えておきましょう。
近年の難易度
Part 2に並んで難易度が高く、上級者であっても連続して失点することが多いパートです。Part 2と同様に、話の流れをしっかり追うことができているかを試される問題です。最新の公式問題集を使って十分に練習をすることをおすすめします。
Part 4
スピーチの形式
1人のスピーチです。
内容
1人の話者がやや専門的な内容のスピーチをします。基本的に、公演や大学の講義のような内容です。例えば、以下のような内容が出題されます。
- テクノロジー
- 地理・歴史
- 環境、環境保護
- 生物学
問題タイプと特徴
10問すべて穴埋め問題であることが多いですが、選択問題などとの組み合わせもあります。スピーチのスピードによって難易度が大きく変わります。長めのスピーチで難易度の高い単語も登場するため、初級者にとっては難しいですが、穴埋め問題がメインの場合は上級者には易しい問題です。
近年の難易度
以前は、専門用語も多く、比較的難易度の高いパートでしたが、近年は多少難易度が下がってきており、初級者の方でも正解できる問題が多数あります。穴埋め形式ですので、スピーチの内容を理解できないからといって諦めることなく、なるべく多くの問題数を正解したいところです。
|
4.1 スコアの計算方法
IELTSのリスニング試験は40問で構成されており、40問中何問正解するかでスコアが決定されます。問題の難易度によって1〜2問の誤差は生じますが、概ね上の表の通り採点されます。
- 39〜40問正解 スコア 9.0
- 37〜38問正解 スコア 8.5
- 35〜36問正解 スコア 8.0
- 33〜34問正解 スコア 7.5
- 30〜32問正解 スコア 7.0
- 27〜29問正解 スコア 6.5
- 23〜26問正解 スコア 6.0
- 19〜22問正解 スコア 5.5
- 15〜18問正解 スコア 5.0
- 13〜14問正解 スコア 4.5
- 10〜12問正解 スコア 4.0
- 8〜9問正解 スコア 3.5
- 6〜7問正解 スコア 3.0
- 4〜5問正解 スコア 2.5
- 3問正解 スコア 2.0
- 2問正解 スコア 1.5
4.2 スペリングの重要性
リスニングの回答は記述式のため、スペリングに注意が必要です。スペリングミスは間違いと判断されますので、普段からスペリングに強くなっておくことが重要です。
ペーパー試験では大文字・小文字の区別はされず、すべて大文字、またはすべて小文字で回答をしてもスペリングさえ正しければ正解になっていましたが、CDIでは大文字・小文字の区別がされますので注意しましょう。
4.3 まとめ
以上まとめると、リスニングのスコアは40問中何問正解できたかで決まります。スペリングミスは間違いと判定されるため、スペリングには十分注意しましょう。
- 40問中何問正解できたかでスコアが決まる
- ペーパー試験では大文字・小文字は区別されない
- CDIでは大文字・小文字は区別される
- スペリングミスは間違いと判定される
|
IELTSのリスニング対策は、まず自分のレベルを知ることから始まります。そのために実際の試験を受けてみるのも一つの方法ですが、公式問題集などを使って実際の問題を解いてみることでも自分のレベルをある程度把握することができます。リスニング・リーディングは前述の通り、正解できた問題数によってスコアが決まるため自己採点が可能です。自分のいまの実力がある程度把握できたら、「目標スコアまであと何問ほど足りないのか?」を確認しましょう。練習では、目標スコアとの差を縮めていくことが基本的な戦略となります。
5.1 Part 1の特徴と目標スコア別対策
Part 1では、2人の話者が、問い合わせなど日常的な対話をしています。電話での会話も多く出題されます。問題形式は穴埋め問題が中心で、人名や地名のスペル、人数や電話番号などの数字、日時や集合場所など、話の主要なポイントとなる単語が問題となっています。会話のなかで、言い直したり、いくつか似たようなオプションが登場したりすることもあるので注意が必要です。3つの選択肢から解答を選ぶタイプの、選択問題もまれに出題されますが、それでも後半のパートに比べるとそれほど難易度は高くありません。
他のパートと比べて格段に易しい問題であるため、どのスコアを目指す方にとっても、Part 1は最も得点しておきたいパートです。しかし、ひっかけ問題も多く、なかには、誰もが間違えやすい問題が1、2問は含まれています。少々のミスは仕方ありません。
6.0以下までのスコアを狙うなら・・・
6-7問の正解を目指しましょう。Part 1は、ひっかけとなるような言葉が多いため、答えと思われるような言葉が聞こえても内容を最後まできちんと聞いて、それが本当に正解かを判断しましょう。また、スペリングミスや単数・複数の間違いなど、いわゆる凡ミスを少しでも減らしましょう。
6.5以上を目指すなら・・・
8〜9問の正解を目指しましょう。中・上級者は、Part 1とPart 4でなるべく多くの正答数を稼いで、Part 2とPart 3でなるべく失点を減らす、というのが基本戦略です。
5.2 Part 2の特徴と目標スコア別対策
1人のスピーカーが、「日常に関する話」をします。問題の範囲は多岐に渡り、なかでも「選択問題」「地図」「状況判断」「分類」などの出題が多いようです。まれに、「図・表の穴埋め問題」が出題されることもあります。
前述の通り、Part 2は近年、最も難易度の高いセクションの1つになっています。特に「選択問題」では、なんらかの点で、ほぼすべての選択肢に該当するような話が出てくるため、単語を中心に聞いていると引っかかってしまう可能性が高くなります。一つ一つの単語は聞き取れなかったとしても、話の流れをしっかり追うことが重要です。
6.0以下までのスコアを狙うなら・・・
各問題文のキーワードを掴みながら、現在話されている箇所を確認していきましょう。表を埋める穴埋め問題や、選択肢通りにそのまま出てくる選択肢などを正確に解答できるようにしましょう。
6.5以上を目指すなら・・・
内容を聞くなかで、問題文の引っ掛けの選択肢がなぜ正解でないのか、という不正解の選択肢の根拠も聞き取りましょう。不正解の選択肢の根拠に気づくことで、より正解の選択肢への確信が高まります。また、質問文の文全体が言い換えられている内容も理解できることを目指しましょう。
「選択問題」の言い換えパターン
出題頻度の高い「選択問題」では、与えられている選択肢は、スピーチの中では以下のように言い換えれられていることが多いですので、知っておくといいでしょう。
もちろん、選択肢と同じ表現が使われることもあります。特に、金額等の数字や、短い言葉、比較的難しい言葉などは言い換えがなくそのまま読まれることが多いようです。
1. 似たような意味の別の言葉に言い換えられている
「jewelry」を「bracelet」に、「weekdays」を「Monday to Friday」に、といった感じで、似た意味の別の単語(または表現)に言い換えられているパターンです。比較的初級者の方でも気付ける語彙レベルの単語が使われていることが多いですので、注意深く聞くことが大切です。
- car vehicle
- job occupation
- weekdays Monday to Friday
- start begin
- cheap inexpensive
- buy purchase
- huge enormous
2. 文全体が言い換えられている
よりレベルの高い言い換えの方法として、文全体が言い換えられていることもあります。同じことを言っていると気づくためには、スピーカーの話を「単語」として聞くのではなく「内容」として理解している必要があります。
- Children must be supervised.
- (子どもは監督されなければなりません)
- ↓
- Adults should not leave children by their own.
- (親は子どものみを残してはいけません)
- She was not aware of the correct location.
- (彼女は正しい場所を認識していませんでした)
- ↓
- She didn't realize where she should have been.
- (彼女はどこにいるべきか気づいていませんでした)
5.3 Part 3の特徴と目標スコア別対策
どのレベルを目指す受験者にとっても、Part 3は最も難易度の高いパートです。学術的な難しい語彙が使われている上に、2人以上の対話で、さらに話が二転三転します。また、選択肢の言い換えも非常に複雑になっているため、ただ英語を聞き取れるだけではなく、話されている内容をきちんと理解する、ということが求められます。Part 3の選択肢の本文での言い換えは、実は「抽象(選択肢)→具体(会話)」がベースになっていることが多いようです。選択肢には比較的抽象的なことが書かれていて、スピーチ(会話)の中で、それがどのようなことなのかを具体的に説明するというパターンがよく見られます。
例えば、選択肢に「間違ったところに立っていた」と書かれていて、会話の中でどのような状況だったのかを具体的に説明したりします。選択肢にある「wrong place」という単語を待っていたのでは、正解ができないようになっているのです。また、一度出てきた名詞は「it」や「they」などの代名詞に置き換えられていることもあります。このように、抽象的な表現の選択肢に対して、会話での具体的な内容をしっかり理解して正解を見つける、というところがPart 3が難易度が高いと感じる理由です。
6.0以下までのスコアを狙うなら・・・
他のパートの正答数が伸びるまでは、重点的に練習をしなくてもいいでしょう。後述のパート別の点数配分を参考に、他のパートでしっかりカバーをしましょう。ちなみに、不正解の選択肢ほど会話の中で聞きやすくなっている傾向があります。どうしてもわからない場合には、本文で聞こえた選択肢を消去し、残ったものを選ぶ、といった大胆な対策をされている方もいます。
6.5以上を目指すなら・・・
リスニングで6.5以上のスコアを目指す方は、Part 3をすべて捨てることはできません。基本は「消去法」で対応しましょう。違うと思った選択肢を消していくと正解率が上がります。1つに絞れなかったとしても、明らかに違う選択肢が消せるだけで正解の確率は大幅に上がります。
7.0以上を目指すなら・・・
可能な名切り、会話の全体の流れを追えるように繰り返し練習をしましょう。特に、選択肢の内容を否定する「not」などが意外と聞きづらいことが多いため、会話全体の流れを追いつつ、細部の情報もなるべく聞き漏らさないようにしましょう。
- She stood at a wrong place.
- (彼女は間違った場所に立っていました)
- ↓
- The place I started it from was on the foot of the mountain, then I noticed I should have gone up somewhere higher in order to have better visibility, so I had to climb up there.
- (山の麓から始めましたが、もっとよく見るためには高いところへ行かなければと気づきました、なので山に登らなければなりませんでした。)
5.4 Part 4の特徴と目標スコア別対策
Part 4では、一人の人が学術的な内容を話します。使われている単語のレベルが上がるため、初心者の方には難しく感じるかもしれませんが、答えに当たる単語などは比較的易しいものが多いです。リスニングは基本的に、問題の内容が上から順番に読まれていくため、解答が必要ではない箇所の文も本文を聞きながら見ていくことで、今どの辺が読まれているのかと言うことを終始確認できます。また、小見出しなども場所を判断する上でのよいヒントとなります。さらに、スクリプトが約6分と長いため、途中で問題文には書いていないような話をしていることもよくあります。そのような箇所に遭遇したとき、今どこが読まれているのかを見失なったかのように感じます。そんなときは落ち着いて次のキーワードが聞こえてくるのを待ちましょう。
6.0以下までのスコアを狙うなら・・・
Part 2と比べて、より得意な方を伸ばしていきましょう。聞きながら問題文をしっかりと目で追い、読まれている箇所を見失わないようにしましょう。万が一見失ってしまった場合は、切り替えて小見出しなどに出てくるキーワードが聞こえるまで落ち着いて待って下さい。また、正解となる単語のなかでは本文中ではっきりと強調されて言われているものもあります。そのような単語を落とさないようにしましょう。なかには比較的難しい単語が正解となるものもありますが、そのような言葉は正解できなくても構いません。
6.5以上を目指すなら・・・
ある程度見失わずに聞き取れる必要があります。文を見ながら読まれている箇所を確認するのに加え、解答する文を確認し、文脈上、文法上適切な言葉を入れられるよう練習しましょう。解答が複数形か、単数形か、などにも気をつけて下さい。
7.0以上を目指すなら・・・
Part 4は実は一番足を引っ張りがちなパートです。難しいが、話の内容さえわかれば解答できるPart 2、3と比べると、Part 4は答えである1語を逃してしまうと解答できないからです。特にPart 2、3で8割ほどの解答ができている方は、Part 4の練習に力を入れうっかりと聞き逃してしまうところが無いよう気をつけましょう。
5.5 目標スコア別の正答数の目安(パート別)
以下の表は、目標スコア別のパート別の目標正答数です。練習をする際には、それぞれのパートで目標スコアに必要な正答数を意識して取り組むといいでしょう。
括弧内に表示している問題数が、Part 1からPart 4での目標正答数です。例えば、目標スコアが6.0の場合、Part 1では7問、Part 2では5問、Part 3では5問、Part 4では6問の正答を目指しましょう。
- 目標スコア 〜5.5
- 目標スコア 6.0
- 目標スコア 6.5
- 目標スコア 7.0
- 目標スコア 7.5
- 目標スコア 8.0〜
- 18〜22問(6+4+4+4)
- 23〜25問(7+5+5+6)
- 26〜29問(8+6+6+8)
- 30〜32問(8+7+7+8)
- 33〜34問(9+8+8+9)
- 35問以上(9+9+8+9)
|
リスニング試験はIELTSの4科目のなかでは最も難易度の低い科目とされてきました。問題形式の幅が少なく、リーディングと比べて語彙も簡単なものが多いためです。しかし近年は、特にPart 2、Patt 3で複雑な内容理解が必要な問題が増えてきています。自習する難しさからも、近年はリーディングよりもスコアを上げにくいと感じている日本人学習者が多いようです。
実際、リスニングの相談に来られる方でリスニングよりリーディングのスコアが高い方も多くなってきています。リスニング試験が難しく感じる理由の一つとして、リスニング力以外のスキルが求められていることが挙げられます。
会話やスピーチの内容を「聞いて理解する」というリスニングスキルが試されるのは当然のことですが、実は、「質問や選択肢を素早く読んで理解する」というリーディング力や、「会話やスピーチの中でどのように言い換えられそうかを予想しておく」という表現のスキル、聞き取った単語を「正しく綴る」というスペリングのスキル、など、IELTSのリスニングでは総合的なスキルが必要とされているのです。
このように、IELTSリスニング試験で求められていることしっかりと理解し対策をしなければ、効果的な得点アップには繋がりません。
|
リスニングの問題形式にはいくつかタイプがあります。公式ウェブサイト では、以下のように問題タイプを紹介しています。
- 1. Multiple choice
- 2. Matching
- 3. Plan, map, diagram labelling
- 4. Form, note, table, flow-chart, summary completion
- 5. Sentence completion
- 6. Short-answer questions
- (Source: IELTS Academic format: Listening )
ただ、実際に問題を解いてみると、必ずしもこのタイプごとに同じアプローチ方法が有効というわけではないことに気が付きます。似たように見える問題でも、キーワードの探し方や特徴が異なるのです。例えば、選択問題(multiple choice)では、3択の選択肢のなかから1つを選ぶタイプ(single choice)と、5択の選択肢のなかから2つ、または3つの解答を選ぶタイプ(multiple choice)があります。それぞれに難易度も注意点も異なります。
プラスワンポイントでは、その問題タイプの難易度、特徴をより実践ベースで捉え、独自の分類をしています。それぞれに、
- どのようなプロセスで問題を解くのが効率的なのか?
- どのような点に注意すべきか?
を考え、以下のように分類しています。
- 1. 穴埋め問題
- 2. 選択問題(シングル)
- 3. 選択問題(マルチプル)
- 4. 地図
- 5. 状況理解のマッチング
- 6. ショートアンサー
7.1 穴埋め問題
一般的にIELTSのリスニング問題のなかで、穴埋め問題が最も得点しやすい問題と言われています。特にこの問題形式は、Part 1とPart 4でよく出題されます。スペルのミスには気をつけて解答しましょう。穴埋め問題で出題される形式は次のようなものです。
- メモ
- 表
- フローチャート
- 文章
7.2 選択問題(シングル)
選択問題のシングル形式の問題とは、3~4つ程度の選択肢のなかから正しい答えを一つ選ぶ問題です。特にPart 2、Part 3で多く取り入れられています。この形式の問題には、選択肢のなかにひっかけ問題が含まれていることが多いため、聴こえてきた言葉が含まれているものを闇雲に選ぶのは避けましょう。問題が読まれる前に、質問文をきちんと理解してその質問の答えとなっている部分を選ぶことが大切です。
7.3 選択問題(マルチプル)
選択問題のマルチプル形式の問題とは、選択肢のなかから複数の解答を選ぶタイプの問題です。この形式の問題は難易度が高く、全ての答えが見つけ出せないこともあるかもしれません。たとえ、聞き逃してしまった部分があり、全ての答えが分からなかったとしても、聞き取った答えについては確実に点数を取るようにし、次の問題に引きずることのないようにしましょう。
7.4 地図
まれにPart 2で出題されます。地図形式の問題では、大学のキャンパスマップ、施設図などがよく出題されます。施設を案内してくれる方の説明を聞いて、地図を完成させていくような問題です。この形式の問題は、難易度にばらつきがあります。方角や物の位置関係に関する単語をしっかりと覚えておくことが大切です。
7.5 状況理解のマッチング
状況理解のマッチングでは、各問題に割り当てられた短い言葉に対して、本文中で言われた内容を複数ある選択肢のなかから選ぶ問題です。選択肢は、全ての問題で同じものから選びます。難易度は高めです。この問題は、選択肢が多いためひっかけとなる選択肢が少ない分、話の移り変わりが速く話についていくのが大変です。また、本文中で言われていることと選択肢での表現が大きく異なることも多いために、本文は理解できたが、選択肢が選べないということもあります。基本的にIELTSのリスニングでメモを取ることはお勧めしておりませんが、この問題に関してのみ、聴こえてきた内容を軽くメモし後ほど見返して選択肢を選ぶ、という方法の方がやりやすいこともあります。
7.6 ショートアンサー
ショートアンサーの問題では、内容に関する短い質問が与えられます。この形式の問題には、必ず「NO MORE THAN TWOWORDS」のように語数の指定があり、語数の指定を守った上で、解答しなければいけません。このような問題は、単語を聞き取る以上に内容の理解が重要なため、難易度は高めの問題と言えるでしょう。
|
8.1 公式問題集で演習を重ねよう
IELTSのリスニング対策で最も効果的なのは公式問題集の演習です。
特に、スコアアップのためには、同じ問題を繰り返し解くことがおすすめです。一度解いた問題を復習し、2−3週間ほどの期間を空けて、もう一度解くような勉強方法を取り入れましょう。
何度か演習を重ねるうちに、答えを覚えてしまうかもしれませんが、覚えてしまっていても構いません。そのような時は、答えを思い出すのではなく、答えの根拠になる部分を明確にしながらリスニングの問題を解いてみましょう。
さらに、問題に正解することだけを目標とするのではなく、話全体を理解できるかどうかという点にも着目しながら勉強を行うと、学習効果が高まります。
8.2 リスニングで必須の語彙を覚えよう
他の英語能力試験と異なり、IELTSリスニングには単語の書き取りがあります。
そのため、たとえ対話の内容が理解できたとしても、正しいスペルが書けなければIELTSでは点数にはつながりません。
その特徴を理解した上で、リスニングの過去問題を取り組む際は、2回以上出てきた単語はIELTSリスニング問題の頻出単語であると捉え、単語のスペルを正しく書けるようにしましょう。
8.3 スクリプトで聞き取れていない音を知ろう
IELTSのリスニング試験で点数を伸ばすためには公式問題集に取り組むことが効果的です。しかし、公式問題集をやるだけでは十分にリスニングの力を身につけることはできません。
リスニングの力を伸ばすためには、一通り問題を解いた後にしっかりと復習をすることが大切です。
復習を丁寧に行うことで、リスニング力を飛躍的に上げることができます。復習では問題のスクリプトを見ながら、実際に何を話していたのか、内容を確認してみましょう。そうすることで、聞き取れていなかった英語の発音を学ぶことができます。
8.4 会話特有の言い回しに慣れよう
IELTSのリスニングでは、複数人が話している対話を聞きとる問題が出題されます。そのなかには、会話特有の言い回しも多く含まれているため、このような会話のフレーズに慣れておく必要があります。
例えば、電話番号を相手に伝える際、電話番号の数字が連続しているとします。その場合は、同じ数字を2-3回繰り返して言うのではなく、“double” “triple”という単語を使って表現します。
このように会話で使う表現があるため、公式問題集のスクリプトを見て復習をしながら、特徴的な会話のフレーズを確認しましょう。
|
9.1 メモを取るより内容を集中して聞こう
IELTSのリスニング試験では、問題は1回しか放送されません。この1回の放送で内容を聞き逃さないためには、メモに時間をかける以上に、話の全体を理解することの方が大切です。
一部の受験生の方は、リスニングを聞きながらメモを残し、後から考える方法を取っていると思います。しかし、この方法でスコアメイキングに繋がっていないようでしたら、メモに集中してしまっているがために、内容を聞き逃しているかもしれません。
どうしても答えに悩んだときには、選択肢問題であれば、絶対に異なる解答にバツ印をつけたり、その時点で聞き取ったことを、簡単にカタカナでメモをする程度にしましょう。
9.2 最後まできちんと聞こう
パート1の穴埋め問題や、パート2、3の選択式の問題では、答えと思われる内容が聴こえてからそれを後に否定する、ということがよくあります。答えになりそうな内容が聴こえたらすぐにそれに飛びつがず、必ず最後までその内容が変わらないかしっかりと聞いてください。
特に、“but”などの逆説の表現がでてきた場合は、その前に言われたことをを覆すような内容が言われることが多いの注意して聞いてください。
9.3 穴埋め問題は語数制限に注意
穴埋め問題には、解答の語数制限があります。このような語数の指定は、各パートのインストラクションに明記してあるため、問題を答える前に、インストラクションに目を通し、必要であれば重要事項にアンダーラインをするなどの工夫をして、確認漏れがないようにしましょう。
「NO MORE THAN TWO WORDS」というのが指示の場合、解答は1語のものもあれば2語のものもあります。
「Write ONE WORD OR/AND A NUMBER」の場合、解答は、1語の単語だけのもの、数字だけのもの、もしくは1語の単語と数字を一緒に書くものがあります。
9.4 単数形と複数形の違いに注意をしよう
IELTSのリスニングではスペルミスの他に、単数形と複数形の間違いも減点対象です。
基本的には、本文で聞こえた通りに書くことが大切です。
また、内容全体を聞き取ることができるようになると、話の流れとして「単数形が適切なのか?」「複数形が適切であるのか?」という点を判断することが可能です。
さらに、穴埋め問題であれば、前後の文脈や穴埋めに必要な語彙数にもヒントが隠されていることがよくあります。文章全体を確認して単数形や複数形の違いを判断しましょう。
9.5 選択問題ではひっかけの選択肢注意
選択問題では、ひっかけの選択肢がたくさんあります。そのため、リスニング問題を聞く際、単語だけを聞き取るような解き方をしていると、間違った選択肢を選びかねません。
リスニングの本文を聞く前に、質問文の意味をしっかりと確認して、質問に合った選択肢を内容から選ぶことが大切です。特に選択肢の内容が読まれた後に“but”などの逆説の表現がでてきた場合は、その前に言われたことを覆すような内容が言われることが多いため特に注意して聞いてください。
以下の3つに注意!
副詞に注意!
副詞は文の動詞を修飾するため、質問文の意味の方向性を変えます。内容を聞く際には、副詞の内容に当てはまるもののみを選びます。例えば質問に、「originally(元来は)」という単語が出てきたとします。本文では最終的に決まった内容等が話されていても、「初めはこうでした」などといった形で元来のことをを話している内容に当てはまる選択肢のみを選びます。
時制に注意!
時制も副詞同様、ひっかけに利用されやすいです。内容を聞く際には、質問の時制に合ったものを選びましょう。
「agree」に注意!
Part 3の対話問題でときおり出てきます。さまざまな内容が言われるなかで、登場人物たちが賛成した内容のみを選びましょう。大抵は、1人が選択肢の内容について話し、もう一人が「そうね」といった形で軽く賛成しているものが多いです。特にこの賛成の相槌を聞き逃しやすいため注意しましょう。
|
10.1 問題の先読みの時間は超重要!
問題の先読みとは、リスニングの問題が始まる前に、質問の内容や選択肢を読んでおくことを意味します。事前に質問や選択肢を理解しておくことで、リスニングを聞きながら答えを見つけやすくなります。
先読みのテクニックを使う場合、パート1のインストラクションの放送が流れているなか、パート2以降の問題を読むことに時間をかける必要があります。そして、パート1の問題が始まった瞬間、パート1に戻りリスニングの内容に集中力しなければいけないため、素早い切り替えの能力が必要になってきます。
先読みテクニックを使うことでリスニング試験の点数向上に繋がることは確実です。しかし、あまり英語に自信のない方であれば、先読みに集中しすぎてしまうと、パート1で点数を落としてしまいかねません。ご自身の英語力と目標点に応じて先読みテクニックを適度に取り入れてみましょう。
10.2 ペーパーベース試験の利点は大きい
ペーパーベースのリスニング試験では、まずはじめに問題用紙に答えを記入することをおすすめします。IELTSのリスニングは1回しか読まれないため、少しでも聞き逃しを減らすためにも、問題用紙から目を逸らさないようにしましょう。また、後から答えを解答用紙に転写することで、スペルミスのチェックができたり、解答欄の記入ミスも防ぐことができます。
ペーパーベースのIELTS試験であれば、リスニング試験の最後に答えを転写する時間が10分間あります。この時間を有効に活用して、解答の転写や見直しをしながら、悩んだ問題を振り返ってみましょう。悩んだ問題でも、話の展開を概ね掴み取っていれば、問題をゆっくりと読むことで、正しい答えが分かる場合もあります。同時に、スペルミスの確認も行いましょう。じっくりと、一つひとつスペルの確認を行い、この時間を使って小さなミスを防ぎましょう。
それに対して、CDIの場合解答用紙に答えを写す必要がないため、最後の確認の時間は2分間しかありません。問題の画面を見ながら、本文が流れている最中にクリックをしたり答えを記入したりしていきます。確認の時間が短いため、未記入の問題があると大変です。なるべく空欄を作らず問題を解いていくことをおすすめします。
10.3 IELTSはイギリス英語だから難しい?
IELTSの試験はイギリスやオーストラリアで広く活用されています。そのため、イギリス英語やオーストラリア英語の発音が多く使われているのは事実です。しかし、出題される問題はイギリス英語やオーストラリア英語には限定されていません。なかには、インド人の英語・日本人の英語なども出題されます。
普段、英語圏に住んでおられる方は、日常生活のなかで様々な国の人の英語に触れる機会が多いと思いますが、日本に住んでおられる方は学校教育で教わったアメリカ英語にしか慣れていない方も多いでしょう。IELTSリスニング対策の際には、公式問題集を解いたり、日常生活で英語のニュースを見たりしながら、色々な英語に慣れていきましょう。
|
11.1 解答の表記についてのお得な知識
穴埋め問題は、イギリス英語のスペルにこだわることはありません。イギリス英語の綴りでも、アメリカ英語の綴りでも、自分が慣れているスペルで解答しましょう。しかし、解答用紙全体を通して、イギリス英語とアメリカ英語のスペル両方が入り乱れるような解答は避けましょう。
また、リスニングの解答の大文字表記、小文字表記も採点には影響しません。文の先頭にくる文字は大文字、などと考える必要はありません。大文字でも小文字でも、慣れていてスペルミスが気付きやすい方で解答しましょう。また、日付が答えになるとき、その記述方法は国によってさまざまです。よって、日付を解答するときには正しい解答が複数あります。
- 24th January
- 24 January
- January 24
- 24 Jan
「January」を「Jan」、「Wednesday」を「Wed」と、一般的に使われているものなら省略して回答することもできます。しかし曖昧なものや、一般的に使われていないと判断されたものは不正解になることがあるため気をつけましょう。
また、選択肢問題で1つの問題から2つ選択肢を選ぶマルチプルチョイスの問題は、正しい解答さえ書けていればどの順で書いても正解になります。また、正解したものが2つのうち1つだった場合は、正解した1点が得点となります。
11.2 聞き逃して頭が真っ白になった場合の対策は?
万が一聞き逃した部分があったとしても、後ろ髪を引かれないことが大量失点をしないための一番のポイントです。どれだけ英語力に長けている人でも、2〜3問の聞き逃しはあって当然のことです。最も重要なことは、その次の問題を落とさないために、話の流れにすぐに戻ることです。
気持ちの問題とも関わってくることもありますが、自分の目標点の達成のためには、何問正解すれば達成できるのかということを頭に入れておくと、何問まで失点してよいのかを計算することができます。その失点を許容範囲として考えることで、答えを聞き逃したときも、気持ちを切り替えて次の問題に臨むことができます。
全問正解しようと意気込んでいると、聞き取れなかったときのショックがとても大きく、その後にも引きずってしまい、結果として多くのミスを出してしまうことになりかねないため、気持ちの切り替えが非常に重要です。
11.3 リスニングは集中力が勝負である
問題の先読みのテクニックの話にも関連しますが、リスニングで最も重要なのは集中力です。たった1回しか聞くことができないリスニングの問題で、先読みのテクニックを使い、パート間の行き来をしたり、パッと次の問題に気持ちを切り替えたりするには、集中力の高さが関わってきます。
そのため、日々の学習でもパートごとに区切って練習する日もあれば、本番のような緊張感を持って、パート1〜4までを通して練習してみるなど、集中力を高めるトレーニングをすることもIELTSリスニングの効果的な対策であると言えるでしょう。
|
いかかでしたでしょうか?IELTSリスニングは、英語のリスニングスキルを上げるとともに、IELTSの問題傾向をきちんと把握し対策ができていることが目標スコアを取る上で重要になります。PlusOnePointでは、常日頃IELTS試験の最新の情報を手に入れながら問題の傾向を研究し、最善の対策法を練り出しています。ご自身での対策が難しく感じている方はお気軽に、IELTS無料学習相談をご利用ください。IELTS学習のプロが、皆様の目標スコア、状況などに合った対策法を親身になってお伺いいたします。
お気軽にお問い合わせください
あわせて読みたい記事

現在形は現在の話ではない?...
2025年11月28日更新
「現在形」という名前から、つい「今起きていること」を表すと思いがちですが、実は英語の現在形は「今この瞬間」を表す時制ではありません。現在形の本質的な役割は、習慣...
記事を読む