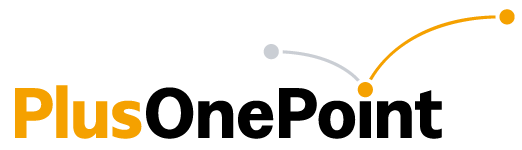「語数が足りないかもしれない」という不安から、ダラダラと長い文章を書いてしまう。IELTSライティングでよく見られる光景です。しかし、目標スコアが6.0以上の方にとって、この戦略は逆効果です。
この記事では、ケネディ大統領のスピーチライターの教えから学ぶ「シンプル・イズ・ベスト」の原則と、それをIELTSエッセイライティングにどう活かすかを解説します。
語数稼ぎの落とし穴
IELTSライティング・タスク2では、最低250語という語数制限があります。この数字を意識するあまり、多くの受験生が「とにかく長く書かなければ」という思い込みに陥ります。
冗長な表現の例
語数を稼ぐために、不必要に長い表現を使ってしまうケースを見てみましょう。
- 冗長な表現の例
- In today's modern world of the 21st century, it is an undeniable fact that cannot be disputed that social media platforms and networking sites have become an integral and important part of our daily lives and everyday activities.
- 今日の21世紀の現代世界において、ソーシャルメディアプラットフォームやネットワーキングサイトが私たちの日常生活や日々の活動の不可欠で重要な一部になったことは、議論の余地のない否定できない事実です。
この文は40語以上ありますが、実質的な内容は非常に薄いです。もちろん、これは極端な例ですが、「In today's modern world of the 21st century」「it is an undeniable fact that cannot be disputed」「integral and important」など、もっとシンプルに表現できるはずのものを、意図的に長く表現していることが伺えます。
簡潔な表現の例
同じ内容を簡潔に表現してみましょう。
- 簡潔な表現の例
- Social media has become an integral part of our daily lives.
- ソーシャルメディアは私たちの日常生活の不可欠な一部になった。
わずか11語で、同じ内容を伝えることができます。そして、こちらの方がはるかに読みやすく、説得力があります。
Less is more(少ないほど良い)
ジョン・F・ケネディ大統領のスピーチライターだったセオドア・C・ソレンセン(テッド・ソレンセン)は、説得力のあるスピーチの第一原則として「Less is almost always more(少ないことは、ほとんどの場合より良い)」を挙げています。
ちなみに、「Less is more.」という表現自体も、完全に書けば「Less is more effective (than more).」(少ない方が、多いよりも効果的である)となりますが、この冗長な表現を削ぎ落として「Less is more.」という3語に凝縮したものです。つまり、この格言そのものが「シンプル・イズ・ベスト」を体現しているのです。
この原則がエッセイに当てはまる理由
なぜ「少ない方が良い」のでしょうか。理由は明確です。
- 簡潔な文章の利点
- 明確性:余分な言葉がないため、主張が明確に伝わる
- 説得力:無駄がないため、論理の流れが分かりやすい
- 読みやすさ:採点者の負担が少なく、好印象を与える
- 記憶に残る:シンプルなメッセージの方が印象に残りやすい
ソレンセンの言葉を借りれば、「誰も『ああ、あのスピーチがもっと長ければよかったのに』とは言わない」のです。これはエッセイについても同じことが言えます。
焦点を絞る
「Less is more」を実践するには、焦点を狭く保ち、直接的に表現することが重要です。同じ内容を少しでも簡潔に表現ができるのあれば、その選択をするべきということです。
明確なテーマと構成
ソレンセンによれば、優れたスピーチは「しっかりとオーガナイズされ、一貫性のある明確なテーマ」を持っています。これはエッセイライティングにも当てはまります。
トピックを明確に示す
エッセイのボディ段落では、トピックセンテンス を通じてあなたの主張を明確に示すことが重要です。読み手は、これから何についての議論を読むのかを最初に知りたいのです。
- 効果的なトピックセンテンスの例
- Social media is fundamentally weakening the quality of human connection by replacing meaningful face-to-face interaction with superficial online engagement.
- ソーシャルメディアは、意味のある対面での交流を表面的なオンラインでの関わりで置き換えることによって、人間のつながりの質を根本的に弱めている。
この一文で、その段落の議題(トピック)と書き手の主張(メインアイデア)が明確に示されています。
表現にも無駄がありません。つまり、読みやすく、記憶に残りやすいのです。
シンプルな言葉で高度な内容を
ケネディとソレンセンは、「聴衆の視野を高める」ことと「言葉を簡潔にする」ことを同時に実現しようとしたと言われています。つまり、高度な内容を、誰にでも理解できる言葉で表現することを目指したのです。
難しい単語を使えばスコアが上がる?
多くの受験生が「普段めったに使わないような難しい単語を使えば高得点が取れる」と誤解しています。しかし、実際には必ずしもそうとは言えません。
- よくある誤解
- 難解な単語を使えば使うほど良い
- 難易度の高い単語の方が知的に見える
- 複雑な構文を使うほうがスキルを見せられる
IELTSの評価基準「Lexical Resource(語彙力)」では、確かに「高いレベルの語彙」が使われているとバンドスコアは上がることが書かれています。しかし、それはあくまでも文脈上適切な単語を正確に使用していることが条件です。逆に言うと、自分が使いこなせない単語を無理に使うことで、文が不自然になるだけでなく、伝えたかった内容を伝えることができなくなる可能性も高まるのです。
短い文と理解しやすい単語
ソレンセンとケネディは、文を短く保ち、平均的な聴衆が理解できる言葉を使うことの重要性を理解していました。
- 平均的な聴衆が理解できる言葉を使う
- 文の長さは15〜25語程度が理想
- 専門用語は必要最小限に
- 明確で具体的な言葉を選ぶ
アイデアこそが鍵
ソレンセンは次のように述べています。「優れたスピーチが優れているのは、強力なアイデアが伝えられているからだ。言葉が高尚で美しく雄弁であっても、アイデアが平凡で空虚であれば、それは優れたスピーチではない」。
これはエッセイライティングにも完全に当てはまります。語彙や文法は知識の誇示ではなく、アイデアを伝えるための手段に過ぎないのです。エッセイの真の価値を決めるのは、内容のほうなのです。
- よくある間違った優先順位
- 1. 難しい単語を使う
- 2. 複雑な文法構文を使う
- 3. 単語と文法ありきで議論を進める
正しい優先順位
本来、優先順位は逆であるべきです。
- 正しい優先順位
- 1. 伝えたい内容を考える
- 2. 自分がコントロールできる範囲の単語を使う
- 3. 自分がコントロールできる範囲の文法構文を使う
まず、何を伝えたいのか、どんなアイデアで読み手を説得するのかを徹底的に考えることが最優先です。強力なアイデアさえあれば、それをシンプルな言葉で表現するだけで十分に説得力のあるエッセイになります。
次に重要なのは、「自分がコントロールできる範囲」で書くことです。見栄を張って難しい単語や複雑な構文を使おうとすると、ミスが増え、高いスコアにつながりません。自分が確実に使える単語と文法で、明確に表現することを心がけましょう。
スコア別の戦略
「シンプル・イズ・ベスト」という原則は重要ですが、あくまで目標スコアによって戦略を変えるほうがいいでしょう。
目標スコア5.5まで:語数の確保が優先
目標スコアが5.5以下の場合、最低語数(250語)を確実にクリアすることが優先になるかもしれません。そのような段階では、語数を稼ぐために多少冗長になっても許容範囲と考えましょう。
- スコア5.5までの戦略
- 多少の冗長さや繰り返しは気にせずに規定語数を確実にクリアする
- 語数が足りない場合は、例を追加する
- 基本的な文法ミスを減らす
目標スコア6.0以上:質の追求
しかし、目標スコアが6.0以上であれば、必要に応じて「「シンプル・イズ・ベスト」の方針も取り入れてみましょう。
- スコア6.0以上の戦略
- 不必要に冗長な表現は避ける
- 可能な範囲で自然な表現を選ぶ
- 自信のない表現をなるべく避ける
- 難易度よりも正確性を優先する
冗長さは内容面にも影響する
冗長あるいは不正確な表現は、内容面にも影響を及ぼすことがあります。
- 内容面への影響
- メッセージが不明確になる
- 論理の流れが分かりにくくなる
- 重要なアイデアが埋もれてしまう
余談:ケネディの就任演説
拙著『英語ライティングの鬼100則(明日香出版社)』(Must 21)のあとがきでも紹介しましたが、私の母校で英語を教えていただいた北川先生は、数カ月に渡ってジョン・F・ケネディの就任演説を使った授業をされました。
高校生には非常にレベルの高い内容でしたが、その洗練された文に深く感銘を受けたものです。今思えば、あの授業で学んだ「シンプルでありながら力強い言葉」の重要性が、今日のライティング指導の基礎になっているのかもしれません。
ケネディの就任演説の中の、「Ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country.」(国があなたのために何をしてくれるかを問うのではなく、あなたが国のために何ができるかを問いなさい)は、誰もが知るあまりにも有名な一節ですが、まさに「Less is more.」を体現した言葉です。短く、明確で、そして記憶に残る。これこそが、優れた文の本質なのです。
まとめ
エッセイライティングにおける「シンプル・イズ・ベスト」の原則について解説しました。
目標スコアが6.0以上の方は、語数を稼ぐための冗長な表現から脱却し、簡潔で説得力のある文を書くことを意識しましょう。
優れたエッセイとは、難解な表現や複雑な語彙で飾られたものではなく、力強いアイデアをシンプルな言葉で明確に伝えられたものなのです。
- 重要なポイントのまとめ
- Less is more. - 簡潔な表現の方が説得力がある
- スコア5.5まで:語数確保が優先
- スコア6.0以上:冗長さを避け、質を追求
- 自信のない表現を使わない勇気を持とう
Ask the Expert
プラスワンポイントでは、IELTS学習に関する疑問やお悩みを相談できる『無料IELTS学習相談』を実施しています。IELTSの学習方法やスコアアップのコツ、勉強計画の立て方などを、経験豊富なカウンセラーが無料でアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。
- 試験を何回受けてもスコアがなかなか上がらない
- 自分自身の学習方法が正しいかどうかを知りたい
- 学習・受講プランの相談に乗ってもらいたい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人
Hibiki Takahashi
日本語で学ぶIELTS対策専門スクール 『PlusOnePoint(プラスワンポイント)』創設者・代表。『英語ライティングの鬼100則』(明日香出版社)著者。1997年に大阪大学医学部を卒業後、麻酔科専門医として活躍。2012年渡豪時に自身が苦労をした経験から、日本人を対象に IELTS対策のサービスを複数展開。難しい文法・語彙を駆使するのではなく、シンプルな表現とアイデアで論理性・明瞭性のあるライティングを指導している。これまでの利用者は4,500名を超え、Twitterで実施した「12週間チャレンジ」では、わずか4週間で7.0、7週間で7.5など、参加者4名全員が短期間でライティングスコア7.0以上を達成(うち2名は7.5を達成)。「IELTSライティングの鬼」の異名を持つ。オーストラリア在住14年、IELTS 8.5(ライティング 8.0)、CEFR C2。
あわせて読みたい記事

エッセイ全体の流れから見るアイデアの妥当性...
2025年11月17日更新
ライティング・タスク2
まずは、このエッセイを見てみましょう。University education should be free for everyone, regardless ...
記事を読む

原因・問題点・影響・解決策の答え方...
2025年12月21日更新
ライティング・タスク2
IELTSライティング・タスク2のCause/Problem/Effect/Solution問題の基本構造から応用まで徹底解説。複数のアイデアが必要な理由、段落...
記事を読む

リーディングで時間が足りない!本当の原因と解...
2025年7月29日更新
ニュースレター
「読むのが遅くて、いつも最後まで解けません」「時間がなくて焦ってしまって、うまく頭に入ってこないんです」このように、リーディングで困っている方、多いんですよね....
記事を読む

IELTSスピーキングが苦手なあなたへ。最初...
2025年7月31日更新
ニュースレター
スピーキングの練習、うまくできていますか?「日本にいて、練習相手がいない」「どうやって練習したらいいかわからない」という声をよく聞きます。確かに、スピーキングの...
記事を読む

語彙強化方法★その2〜実践ベースで単語を覚え...
2024年11月18日更新
ニュースレター
こんにちは^^ プラスワンポイントのルイです! 今日もIELTS学習、がんばって取り組んでいますでしょうか? ちょっと前回から時間が空いてしまいましたね。今年は...
記事を読む

ライティングサミット 第181週モデルアンサ...
2025年12月7日更新
ライティングサミット
ライティングサミット受講生限定コンテンツです。閲覧にはライティングサミット受講生の権限が必要です。...
記事を読む