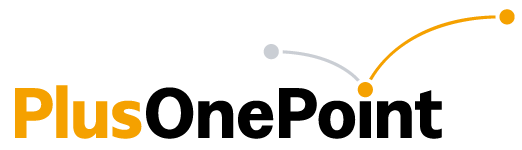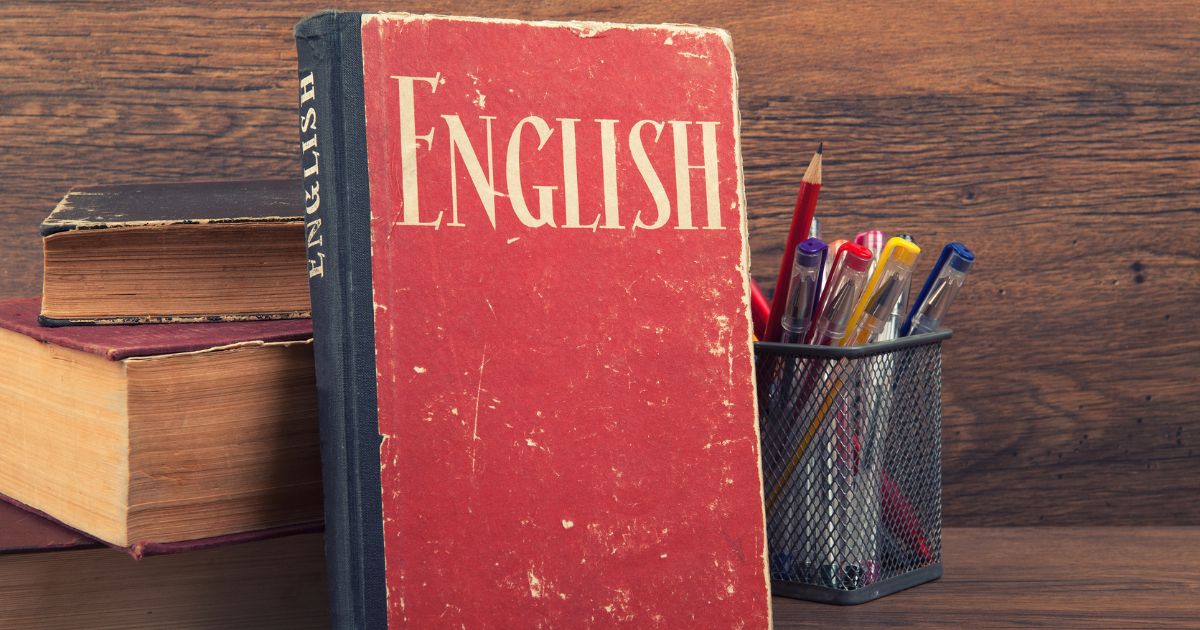「ソーシャルメディア」という言葉は、IELTSライティング・タスク2でも頻繁に出題されるトピックです。しかし、多くの受験生がこの言葉の本質を正確に理解せずにエッセイを書いてしまい、的外れな議論をしてしまうケースが見られます。
この記事では、ソーシャルメディアの本質的な特徴を理解し、説得力のある議論を展開するためのポイントを解説します。
典型的な出題例
まず、ソーシャルメディアに関する典型的な出題例を見てみましょう。
- タスク例
- Some people believe that social media contributes to maintaining social relationships. Others, however, argue that it is replacing face-to-face communication and damaging social relationships. Discuss both views and give your own opinion.
- 一部の人々は、ソーシャルメディアが社会的な関係を維持するのに役立つと考えています。しかし一方で、ソーシャルメディアは対面でのコミュニケーションを置き換え、社会的な関係に悪影響を与えていると主張する人もいます。両方の見解について議論し、自分の意見を述べなさい。
このような課題でエッセイを書く前に、「ソーシャルメディア」とは何かを正確に理解しておく必要があります。なぜなら、ソーシャルメディアの本質を理解していないと、的外れな議論をしてしまう可能性があるからです。
メディアとは?
「ソーシャルメディア」を理解するために、まず「メディア」という言葉の意味から確認しましょう。
メディアの定義
「メディア」とは、情報や意思を伝達する媒体のことを指します。英語の「media」は「medium(媒体)」の複数形で、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など、情報を人々に届けるための手段全般を指します。
従来のメディアの特徴
従来のメディアでは、情報の流れは一方向でした。つまり、新聞社やテレビ局といった「発信者」が情報を作成し、読者や視聴者である「受信者」がその情報を受け取るという構造です。受信者は情報を受け取るだけで、自ら情報を発信することはほとんどありませんでした。
- 従来のメディアの特徴
- 発信者(新聞社、テレビ局など)→ 受信者(読者、視聴者)
- 情報伝達の方向性は一方向であった。
ソーシャルメディアの本質
では、「ソーシャルメディア」とは何でしょうか。
ソーシャルメディアの定義
「ソーシャルメディア」とは、ユーザー自身が情報を発信・共有し、他のユーザーと双方向にやり取りできるメディアのことです。Facebook、X、Instagramなどがその代表例です。
2つの本質的な特徴
ソーシャルメディアには、従来のメディアとは異なる2つの本質的な特徴があります。
- ソーシャルメディアの本質的な特徴
- 特徴①:双方向の情報伝達
- 誰もが発信者にも受信者にもなれる。ユーザーは単に情報を受け取るだけでなく、自ら情報を発信したり、他のユーザーの投稿にコメントしたりできる。
- 特徴②:ユーザー同士のつながり
- ユーザーは友達やフォロワーとつながり、その人たちの投稿を見たり、自分の投稿を見てもらったりすることで、ネットワークを形成する。人々の社会的なつながり(social)を基盤としている。
SNSは和製英語?
日本では「SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)」という言葉がよく使われます。しかし、この「SNS」という略語は、実は和製英語です。
英語圏では「SNS」という略語はほとんど使われず、代わりに「social media(ソーシャルメディア)」や「social networking sites(ソーシャルネットワーキングサイト)」という表現が一般的です。特に「social media」が最も広く使われている表現です。
- SNSは和製英語
- 英語では、「SNS」ではなく「social media」を使いましょう。
ウェブの進化とソーシャルメディア
少し余談になりますが、ソーシャルメディアの登場はインターネットの進化と密接に関係しています。「ウェブ1.0」と「ウェブ2.0」という概念を通して、この進化を理解してみましょう。
ウェブ1.0の時代
「ウェブ1.0」とは、インターネットの初期段階を指します。この時代のウェブサイトは、企業や組織が情報を一方的に発信し、ユーザーはその情報を閲覧するだけという構造でした。ユーザーが自ら情報を発信したり、他のユーザーと交流したりすることはほとんどできませんでした。
つまり、「ウェブ1.0」は従来のメディアと同様に、一方向の情報伝達が主流だったのです。
ウェブ2.0への進化
2000年代に入ると、インターネットは「ウェブ2.0」と呼ばれる新しい段階に入りました。ウェブ2.0の特徴は、ユーザー自身が情報を発信・共有できるようになったことです。
ブログ、掲示板、そしてソーシャルメディアなどがその代表例です。「ウェブ2.0」では、ユーザーは単に情報を受け取るだけでなく、自ら情報を作成し、他のユーザーと共有することができるようになりました。
- ウェブの進化
- ウェブ1.0/従来のメディア:一方向の情報発信
- ウェブ2.0/ソーシャルメディア:双方向の情報発信(ユーザー参加型)
ソーシャルメディアは、まさにこの「ウェブ2.0」の代表的な存在と言えます。ユーザーが自由に情報を発信し、他のユーザーと交流できる点で、ウェブ2.0の特徴を体現しているのです。
よくある間違い
ここまで、ソーシャルメディアの本質は「双方向の情報発信」と「ユーザー同士のつながり」にあることを説明してきました。しかし、近年のソーシャルメディアは多彩な機能を搭載しているため、本質的な特徴とは異なる機能に焦点を当ててしまうことがあります。
本質から逸脱した議論の例
以下は、ソーシャルメディアの本質を捉えていない議論の例です。
- 問題のあるエッセイ例
- Social media plays a significant role in keeping people connected in modern society. Platforms such as Facebook and Instagram provide features like direct messaging and video calls, which allow users to communicate easily without needing to meet in person. These tools make it more convenient to keep in touch with friends and family, regardless of geographic distance.
- ソーシャルメディアは現代社会において人々をつなぐ重要な役割を果たしています。FacebookやInstagramのようなプラットフォームは、直接メッセージやビデオ通話などの機能を提供し、ユーザーが物理的に会う必要なく簡単にコミュニケーションを取ることができます。これらのツールにより、地理的な距離に関係なく、友人や家族とのつながりを維持することが便利になります。
何が問題なのか?
確かに、多くのソーシャルメディアには、ユーザー同士が個別にメッセージをやり取りできるDM(ダイレクトメッセージ)機能やビデオ通話機能があります。しかし、これらの機能は、本来のソーシャルメディアの特徴である「ユーザーによる情報の発信・共有」とは異なります。
DMは特定の個人間でのプライベートなやり取りであり、他のユーザーには見えない閉じたコミュニケーションです。これは、むしろ電子メールや従来のメッセージアプリと同じ性質を持っています。
- DM機能の性質
- ソーシャル(社会的)ではなく、プライベート(私的)
- 情報の公開・共有ではなく、個別のやり取り
- 広範なユーザーとのつながりではなく、1対1のコミュニケーション
ソーシャルメディアの本質を理解していないと、このようなズレた議論をしてしまう可能性があります。
本質に基づいた議論の例
では、どのような議論をすべきでしょうか。ソーシャルメディアの本質である「ユーザーによる情報の発信・共有」や「広範なユーザーとのつながり」に焦点を当てる必要があります。
適切な論点の例
例えば、以下のような論点が考えられます。
- ソーシャルメディアの本質に基づいた論点
- 対面で会話する代わりに、ソーシャルメディアに投稿して自分の近況を共有するようになった
- 友人と直接会って話す代わりに、その人のソーシャルメディアの投稿を見ることで近況を知った気になっている
- ソーシャルメディアの「いいね」やコメントが、実際の会話の代わりになっている
- 多くの「フォロワー」との浅いつながりが、少数の親しい友人との深いつながりを置き換えている
改善されたエッセイの例
これらの論点に基づいて書かれたエッセイの例を見てみましょう。
- 改善されたエッセイ例
- It is true that social media helps maintain social relationships by allowing users to post updates, share photos, and comment on others' posts. These features enable users to stay aware of their friends' and family's lives even when they cannot meet in person, strengthening connections through ongoing presence and mutual support. However, the fact that social media is replacing face-to-face communication and thus weakening relationships is a serious concern. Users may rely on likes, comments, or viewing posts to feel connected, resulting in shallow interactions that lack the depth of direct conversation. This reliance can leave people feeling isolated, with superficial ties to many acquaintances while reducing engagement with close friends.
- ソーシャルメディアは、ユーザーが近況を投稿したり、写真を共有したり、他人の投稿にコメントしたりすることを可能にすることで、社会的な関係を維持するのに役立つのは事実です。これらの機能により、たとえ直接会うことができなくても、友人や家族の生活を把握することができ、継続的な関わりと相互支援を通じてつながりを強めることができます。しかし、ソーシャルメディアが対面でのコミュニケーションを置き換え、それによって関係を弱めつつあるという事実は深刻な懸念です。ユーザーは「いいね」やコメント、投稿を見ることでつながりを感じることに頼る場合があり、その結果、直接の会話がもたらす深いつながりを欠いた浅い交流になってしまいます。このような依存は、人々が多くの知人とは表面的な関係しか持たず、親しい友人との関わりが減ることで孤立感を抱く原因にもなります。
このエッセイでは、ソーシャルメディアの本質的な機能(投稿、共有、コメント)に焦点を当て、それらが対面コミュニケーションをどのように置き換えているかを議論しています。DMやビデオ通話といった付加的な機能ではなく、ソーシャルメディアの核心的な特徴を基に議論を展開しているため、より説得力のある内容になっています。
まとめ
ソーシャルメディアの本質と、それに基づいた議論の組み立て方について解説しました。
エッセイで説得力ある議論を展開するためには、まず対象となる概念の本質を正確に理解することが重要です。ソーシャルメディアについて論じる際には、その本質である「情報の公開・共有」と「広範なユーザーとのつながり」に焦点を当て、付加的な機能(DMやビデオ通話など)と混同しないように注意しましょう。
本質を理解することで、より深く、より説得力のある議論ができるようになります。
- 重要なポイントのまとめ
- ソーシャルメディアの本質は「双方向の情報発信」と「ユーザー同士のつながり」
- 従来のメディアは一方向、ソーシャルメディアは双方向
- 「SNS」は和製英語、英語では「social media」を使う
- DM機能やビデオ通話は本質的な機能ではない
- 投稿、共有、コメントなど本質的な機能に焦点を当てる
- 概念の本質を理解することが説得力ある議論の鍵
Ask the Expert
プラスワンポイントでは、IELTS学習に関する疑問やお悩みを相談できる『無料IELTS学習相談』を実施しています。IELTSの学習方法やスコアアップのコツ、勉強計画の立て方などを、経験豊富なカウンセラーが無料でアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。
- 試験を何回受けてもスコアがなかなか上がらない
- 自分自身の学習方法が正しいかどうかを知りたい
- 学習・受講プランの相談に乗ってもらいたい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人
Hibiki Takahashi
日本語で学ぶIELTS対策専門スクール 『PlusOnePoint(プラスワンポイント)』創設者・代表。『英語ライティングの鬼100則』(明日香出版社)著者。1997年に大阪大学医学部を卒業後、麻酔科専門医として活躍。2012年渡豪時に自身が苦労をした経験から、日本人を対象に IELTS対策のサービスを複数展開。難しい文法・語彙を駆使するのではなく、シンプルな表現とアイデアで論理性・明瞭性のあるライティングを指導している。これまでの利用者は4,500名を超え、Twitterで実施した「12週間チャレンジ」では、わずか4週間で7.0、7週間で7.5など、参加者4名全員が短期間でライティングスコア7.0以上を達成(うち2名は7.5を達成)。「IELTSライティングの鬼」の異名を持つ。オーストラリア在住14年、IELTS 8.5(ライティング 8.0)、CEFR C2。
あわせて読みたい記事

wouldを多用してしまう理由...
2025年12月19日更新
ライティング・タスク2
IELTSライティングで日本人学習者が頻繁に犯すエラーの一つが「would」の過剰使用です。「I would like to say」「It would be ...
記事を読む
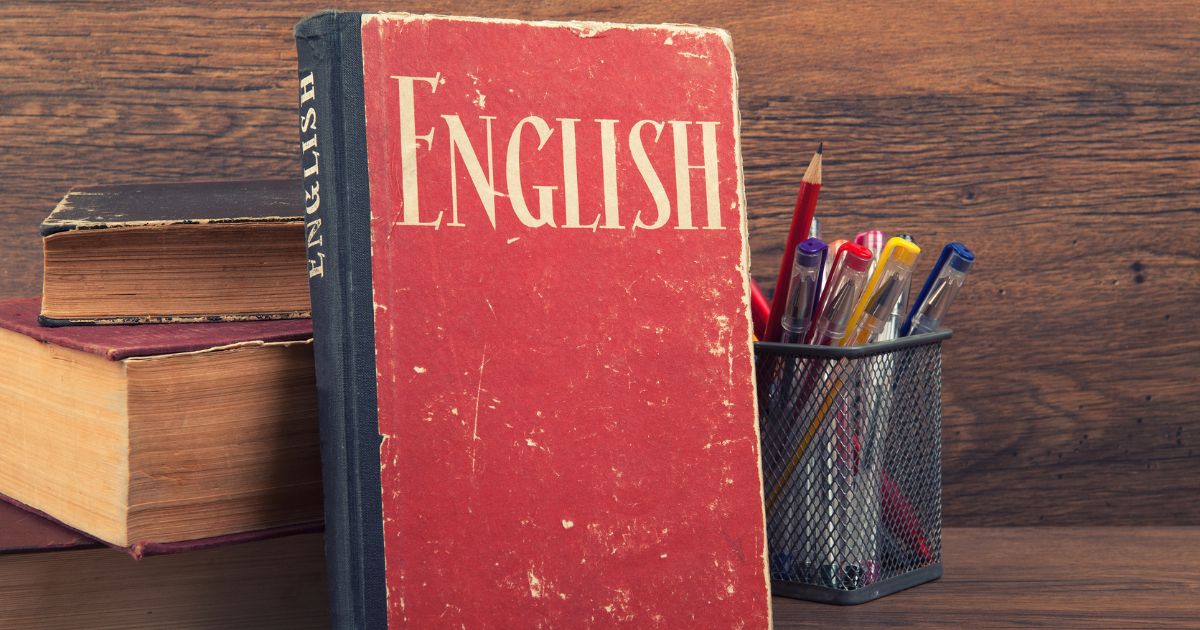
herd mentality | IELTS...
2025年11月14日更新
語彙・表現
IELTS頻出表現「herd mentality」の意味、使い方、例文を詳しく解説。集団心理や社会現象を表現するこの重要な概念をライティング・スピーキングで効果...
記事を読む

PlusOnePointオンラインサロンIE...
2021年8月1日更新
紹介記事
どうもこんにちは。ヒロキです。今回は僕自身所属していた『IELTS SQUARE』というオンラインサロンがありました。で、そのオンラインサロンがなぜ良いのかとい...
記事を読む
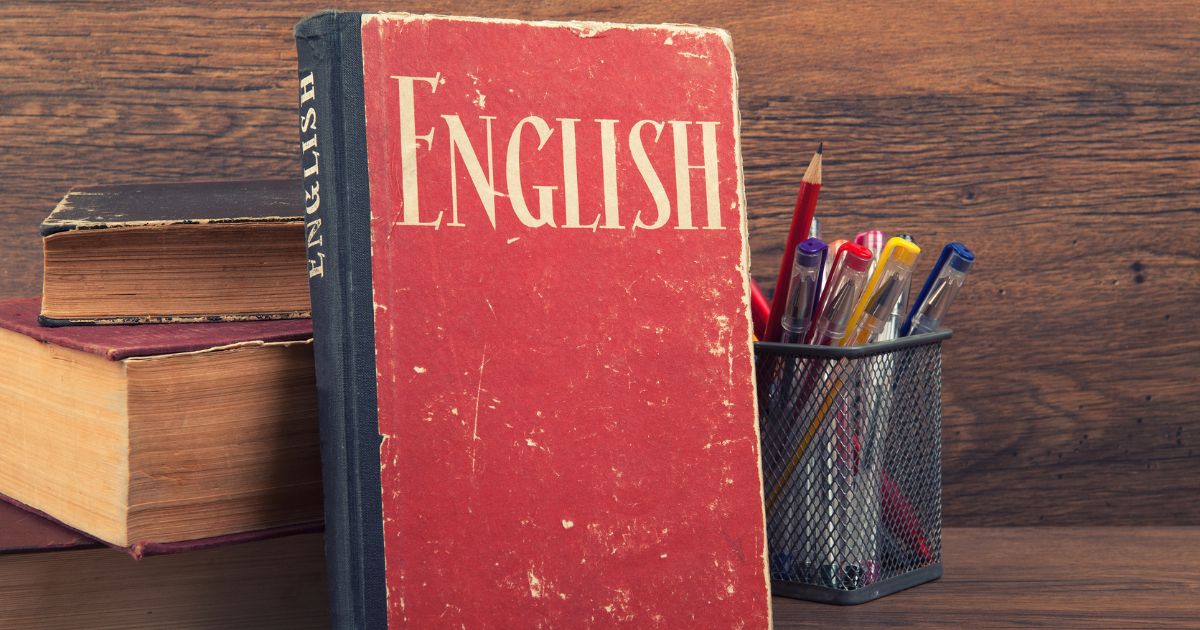
turn over a new leaf |...
2025年11月14日更新
語彙・表現
IELTS頻出表現「turn over a new leaf」の意味、使い方、例文を詳しく解説。新たなスタートや改心を表現するこの重要なイディオムをライティング...
記事を読む

最上級・ONLYなどの極論に対するagree...
2025年11月25日更新
ライティング・タスク2
IELTSライティングのタスク2の問題の中には、いわゆる「極論」を取り上げるものがあります。極論とは、以下のような表現がタスクの中に含まれているものです。all...
記事を読む

表現のブラッシュアップ(1)...
2025年11月17日更新
ライティング・タスク2
IELTSライティング・タスク2の表現のブラッシュアップ練習法を解説します。...
記事を読む